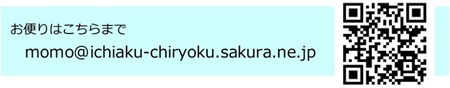一握の知力 > 山之辺古文書庵 > 味覚を問うは国賊 > 壱拾八 1962年のブラームス
壱拾八 1962年のブラームス
書籍の森は何処までも幽遠。分け入る路は幾通りもあるが、どの路を辿ってもその一番奥まった辺りに、様々な知恵と真理を秘めているように思われた。いやそれだけでなく、そこかしこの脇道には神秘や魔法が、花や果実の陰には虎や魔物が潜んでいる様であった。
安くて小さくて渋くて、どれも同じような顔つきをしている文庫版が、久しく少年の心を捕らえていた。ところがある時彼は、古本屋さんでばら売りしている全集・選集の類いが、もっと安上がりだ、ということに気付く。慣れてくると、旧字体・旧仮名遣いの古い書物の方がずっと素敵だ。たいてい振り仮名が振ってあるので、誰にでも読める。
古本屋はお店そのものがミステリーだった。
『柳田国男全集 書簡集2』の隣が『カラー版 東洋秘画大系』であったりする。ある時思い切って、秘画大系の並びにある本を開いてみたら、全身が刺青で褌一丁の中肉男が、痩せた青年を膝に抱いていた。青年は薄目をあけて恍惚の表情である。期待したものとはかなり違ったので閉じようとしたが、隣で書簡集を読んでいたはずのおじさんが、私の拡げたページをじっと覗き込んでいる。人の鼻面の先で本のページを閉じるような不作法はしたくないので、しばらくページを拡げたままにしておいた。ところが何時まで経っても、おじさんはこちらを見ている。視界の隅で窺うと、おじさんが物色しているのは、何と!、本ではなく私の方だった。
本を売るということ以外の、古本屋さんの存在意義と、書簡集と秘画大系が並んで置かれている理由を、私は十四歳で知ったわけである。他の古本屋さんを巡ってみたが、秘画大系の類はきまって店の入り口近く、すぐに通りへ逃れられるあたりに置かれていた。二人の趣味が合わなかった場合の、華奢な美青年の安全を考慮してのことであろうか。大いなる偏見をもって言うのだが、おじさんたちは小柄であっても、いざという時の力はすごいのだ。
もしかすると、僕たちが知っている商業的なおかまさんは、実は目くらましの存在であり、おじさんたちは古本屋さんを連絡アジトにして、一大シンジケートを形成しているのではないか。普段それしか無いと思って見ている「表の市民社会」と重なりあって、実は何重にも裏社会が存在している。確かにそうだ、何よりも効率を重視する表社会の必要だけで、これだけ多くの人々が、来る日も来る日も、忙しげに行き来する必要なぞあるものか。私は十二分に納得して、行き交う人々や通り過ぎる市電を見やった。あっ、いま妙に眼の血走った男が通り過ぎた。あの運転手は前を見ずに、歩道ばかり見ているぞ。
しかしこの作文のタイトルの通り、私は他の何よりも音と遊ぶことが好きだった。この頃すでに西洋古典音楽に親しみだして、約二年が経とうとしていたが、それはまだまだ子供らしい無邪気な好奇心にとどまっていた。それは無理のないことで、このジャンルでは、貸本屋、古本屋、映画館、雑誌というようなソフトウエアの供給源がまだまだ未発達であった。クラシック音楽は一部の人たちの慎ましやかな趣味のレベルにとどまっていた。
前に述べたとおり、学校でそれを教わるにも関わらず、当時のフツーの中学生が西洋古典音楽に接する機会はまずなかった。家庭には西洋音楽的要素は皆無。学校で教わる音楽は唱歌の域を超えなかった。ラジオは歌謡曲で、ロカビリーは不良のものだった。
歌声運動というものがあることを知ったが、歌われている歌は官能性に乏しく、自分は結構毎日を楽しく過ごしているのに、歌を歌うときには急に「可哀想な民衆」のふりをしなければならないのは、相当に無理があった。歌が終わると、封建的な歌や資本主義的な音楽は、断固として否定されなければならないといった議論が、歌以上ににぎやかに交わされた。まだ良く知りもしないことを否定するのはおかしいと感じたし、そもそも歌われている「未来のための歌」というものは、個人の情感を歌わずに、共同幻想的な観念を煽り立てる点で、旧来の軍歌とそっくりだと思った。実際、歌詞の語彙カテゴリーが違うだけで、リズムや節回しなども酷似しています。
名曲喫茶というのがあって、フルトヴェングラーやカール・リヒターが立派な装置で再生されていた。カフカとかドストエフスキーなんかを眺めながら、葬式の通夜みたいな雰囲気で聴いているから、そんなに嫌なら聴きにこなければ良いのにと思ったが、実はそうするのが礼儀なので、彼らは口も利けないぐらいカンドーしているのだそうな。ほんまかいな。
ジャズ喫茶になるとお客は更にシーンとしていた。こちらの静寂は殺気立った沈黙であった。殺気はカウンターの店員とお客の間に、またお客同士の間に張りつめていた。この空間においては、他の人が感動したものには、間違っても私は感動してはならない、という鉄の規則があった。わざわざ自分の孤立性を確認するために来ているようだ。こちらのお客は、読みやすいのだが結局何のことだかよく分からないフランスものを手にしていたが、連れているお嬢様は、確かに名曲喫茶より色っぽかったな。名曲喫茶のような、お母さんのおふる、ありがとう、みたいな眼鏡もかけてないしね。しかし明らかに未成年とお見受けするのに、煙草をプカプカ吹かして(別に良いんだけれど仕草がぎこちない)たまに口を開くと大変なしゃがれ声だったりする。
つまり私としては、この時代の音楽は、風俗として述べることしかできない。
大阪では朝比奈隆さんと大阪フィルが孤軍奮闘しておられた。当時、定期演奏会の座席の幾つかを、子供たちに提供するという素敵な仕組みがあって、森本君と私はせっせと応募の往復葉書を書いた。復信の葉書はたいてい『入場券』のスタンプが押されて帰ってきた。よほど応募者が少なかったのだろう。何か自分たちだけで権利を独占しているような気がして、演目によほど馴染みがない場合は応募を自主規制していた。
朝比奈さんは名曲百選でプログラムを埋めるようなことをしなかった。新しい定番の拡大と確立を目指しておられたと思う。ブルックナーの第七交響曲やストラヴンスキーのペトルーシュカを指揮する、朝比奈さんの後姿を良く覚えている。ストラヴィンスキーはさっぱり分からなかったし、ブルックナーも図書館の名曲解説全集でしっかり予習していったのだけれど、良く分からなかった。予習したって分かるようなものじゃないけれど。
周りの大人たちも演奏が終わると、えっ終わったの、てな感じで一斉に拍手をしていた。感激のあまりのブラボーでは決してなかった。でも朝比奈さんの先駆的な努力、我慢して聴く聴衆、この「我慢の継続」がその後、聴衆の聴く力の基礎づくりをしていると思う。自分がその一人であったことを誇りに思っておこう。朝比奈さんはその最晩年、大阪フィルとのブルックナーで大ブレイクする。その40年も前に中学生の私が、朝比奈ブルックナーを聴いていることは話のネタぐらいにはなる。朝比奈さんとペトルーシュカの取り合わせには、驚く人も多いだろう。
* * *
状況の変化は、1962年にやってきた。私的にというだけでなく、実際に社会的にも一つの流れが出来つつあった。うまく波動のピークが合ったのだ。
吉永小百合さんといえば日本を代表する大スターである。その吉永さんのイメージを決定づけた映画といえば、浦山桐郎監督の『キューポラのある街』でしょうね。矛盾した言い方になるが、おそらく『キューポラのある街』を見たことのない人でも、映画スター吉永小百合さんに、川口の街の中学3年生ジュンの姿を見ていると思う。それぐらい時代のイメージと象徴性の表出に優れた映画だと思う。私だってレンタル・ビデオで一回見たきりだけれど、こまごまと覚えているものね。
まだまだ貧しかった日本。しかし高度成長が始まると、将来に対する希望も見え隠れするようになる。と同時に旧来の大人の世界が瓦解し、新しいひずみも現れだした時代。そこでジュンはたとえ貧しくとも「正しく明るく朗らかな少女の鑑」のような存在として描かれる。
映画の終盤、吉行和子さんが自分の働く工場を、ジュンに案内する場面がある。その工場は労働組合がうまく機能している大きな工場で、仕事があければ女工さんたちは歌声サークルで歌っていたりする。閉塞的な旧社会にはない自由な雰囲気、未来への希望が感じられる。それを見てジュンは、父親(東野栄次郎さん、後の黄門さま、こと水戸光圀公なるぞ)が高校に行けと言うのは、再就職が決まって上機嫌の父親の戯言に過ぎないことを見きわめ、吉行和子さんと同じように、定時制高校に通って大工場の組織的労働者になることを決心する。これで賢くも、中卒ですぐ旧構造の師弟関係中で働いて、閉塞構造の連鎖に取り込まれることを逃れるのである、
今の感覚で見れば歌声サークルだけが少し恥ずかしいが、全体は極めて自然に肯定的に描かれている。この映画の音楽があの黛敏郎さんだと知ると、さらに驚かされる。
また一方ジュンは、映画の中ほどで、ちょっとプチ・ブルジョアしている(今や、完全に死語か?)級友の家を訪問したりしている。夕刻、級友と二人で二階の窓から遠くを見やっていると、メランコリックに歩みを進めるような、とても美しい音楽が聞こえてくる。級友は、あれは、兄が聴いているの、兄の好きな曲なの、と説明する。
二人は自分たちの希望をその中に聴くように、じっと黙して遠くを眺めつづける。確か映画では、友人は曲名を言わなかったと思うが、実はブラームス『交響曲第4番ホ短調 作品98』、その冒頭だった。
この映画の音楽担当である黛敏郎さんは、当時の「正しく明るく朗らかな」若者たち、つまり新しい時代のモラル・リーダーたちが、心から共感できる音楽として『歌声サークル』を選んでいる。また音楽に対してもう少し意識的な若者なら、ぜひ聞きとってほしい音楽として、ブラームスの交響曲を選んでいる。時代の音楽的な局面の典型を提示しており、気鋭の作曲家としてまことに正鵠を得た選択だと思う。
『キューポラのある街』は浦山桐郎監督の第一回監督作品。彼のお師匠さんである今村昌平さんとの共同脚本。1962年の公開である。
映画の終盤、吉行和子さんが自分の働く工場を、ジュンに案内する場面が
映画の中ほどで、ちょっとプチ・ブルジョアしている
この年、東京に新しいオーケストラ読売日響が設立された。その準備の状況は新聞から刻々と伝わってきた。アメリカから指揮者を招聘し、初演を目指してトレーニングを開始した、という記事も覚えている。その指揮者の名は、ウィリス・ペィジさんと言い、私の聞いたことのない名前であった。その後何度か、彼の評価が新聞に載る。
曰く、ウィリス・ペィジ氏は有能なオーケストラ・トレーナーである、彼の薫陶のもと読売日響は、必ずや素晴らしき歴史の幕を開けるであろう。また別の批評家曰く、オーケストラの立ち上げには楽曲の指揮以上の力量がいる、ペィジ氏では明らかに役不足である。正反対の意見である。一体どっちやねん?
オーケストラの練習をほんの少し立ち聴きしたくらいでは、何も判断できないと言うのが本当であろう。仮に妙な音楽が鳴っていても、指揮が拙いのか、団員が拙いのか、楽曲そのものが不出来なのか、見当など付かないはずだ。練習の段階や会場のソノリティによっても全く違ってきこえる。だからこれは批評家の音楽的力量以前のモラルの問題である。せっかくオーケストラを作るという理念のもと、期日の限られた必達目標に向かって多くの人たちが努力していているのに、その努力に水をさしている。全く礼儀を弁えない輩なのだ。
この馬鹿げた記事を読んで、私は断固として、ウィリス・ペィジ名指揮者説を支持する決意をした。その根拠は、新聞の写真で見るウィリス・ペィジさんは、当時大人気だったアメリカの医療現場ドラマ『ベン・ケーシ』の、ヴィンセント・エドワーズさんにそっくりだったからである。男、女、誕生、死亡、そして無限。ベン・ケーシー医師は、当時まだ先端技術であった脳外科手術を必ず成功させ、患者のメンタル・ケアまでしてしまうスパーマンだったのである。
演奏会が近づくと次々と、初演及び日本初ツアーの曲目が紹介されていった。それは大阪で朝比奈さんが黙々と続けておられた、西洋古典音楽の新しい定番の創造とほぼ重なる内容だったと思う。
その中に、ブラームス『交響曲第一番ハ短調 作品68』が含まれていた。それで私はクラシック音楽の神髄に触れたのである。
読売日響の大阪公演は、大阪フィルの定期演奏会と同じように、生徒・学生が葉書で応募すると、フリーのチケットが抽選で貰えることになっていた。しかも二枚セットで。さすがにこちらは人気が高かったようで、私は抽選にもれてしまった。しかし森本君はきっちりと二枚セットを手に入れた。執念の差であろう。
公演が近づいたある日、森本君は私に申し訳なさそうに言った。
今までのお付き合いから考えて、当然君を誘うべきなのだが、実は私には好きな女性がいる。彼女を誘おうと思う。どうか許してくれたまへ。
その日から私の心配が始まった。森本君は風貌も典型的なオタク風で、女の子にもてるタイプであるとはお世辞にも言えなかった。森本君、ごめん、ごめんね。ソー・ユー・フーに見ていたんだ。デートに誘うといったって彼のことだ、彼女が一人でいるときにそっと近づいて、さりげなく囁く、などと言った芸当はできないだろう。衆人環視の中で彼女の前へずかずかと歩み寄り、深々と一礼して、まことに不躾であるが、よろしければ明晩、音楽会へご一緒して頂く訳には参らぬか、と大声で叫ぶだろう。仮に、あくまで仮にだけれど、相手が彼のことを憎からず思っていても、謹んでお受けいたしますとは、みんなの手前言えないだろう。
もし彼女が拒否したら、と言っても、拒否しないという可能性は限りなく零に近いと思われるのだが、もし彼女が拒否したら、あーっ、僕はたった一人の娘の愛さえも、得るこのできぬ男だ、これから先どの様な希望が見いだせようか、僕は死ぬ、止めないでくれたまへ、とか喚いて、建物の縁へ走り出すに相違ない。口もろくすっぽ回らない年齢から、シェクスピア名作集なんぞ読むから、こういうことになるのだ。その時放っておいても、死ぬようなことはまず無いだろうが、君は一度は僕を見限った男だ、などと言って終生私を攻め続けるに相違ない。困った、困った。
しかし時は非情に流れ、コンサートの当日となる。だが森本君は平然としている。何の変化も見せない。その彼女とやらには、快諾を得たのだろうか、それともまだ、申し入れをしていないのだろうか。どっちなんだ、お前。とうとう学校は終業となる。では、さらばじゃ、と教室を後にする森本君。
翌朝の教室。もし彼女にふられていたら、彼をどう慰めるべきか。いい案も浮かばすそわそわしていると、彼が教室に入ってきた。眼が吊り上がっている。これはヤバイ。
しかし私が、昨日はどうだったと訪ねるより前に、彼は叫んだ。
ぶっ、ぶっ、ブッ、 ブ、…… 、ブラームスは凄いぞ!
私は今日に至るまで、彼女との顛末がどうなったのか知らない。彼女の名前も知らない。
―― 壱拾八 1962年のブラームス (了)
―― Page Top へ
―― 次章へ
◆◆◆ 2024/04/18 up ◆◆◆
『一握の知力』 TopPage へ
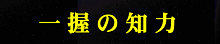
『山之辺古文書庵』 総目次 へ

『味覚を問うは、国賊!』 目次へ

大阪では朝比奈隆さんと大阪フィルが

ベートーヴェン『交響曲第2番』
北ドイツ放送交響楽団(1960)
浦山桐郎監督の『キューポラのある街』

『キューポラのある街』(1962)
確か映画では、友人は曲名を言わなかったと思うが

"Johannes Brahms"(1833〜1897)
その指揮者の名は、ウィリス・ペィジさんと言い

”Willis Page”(1918〜2013)
当時大人気だったアメリカの医療現場ドラマ『ベン・ケーシ』の

"Vince Edwards"(1928〜1996)
『ベン・ケーシー』
オープニング
↑クリック
『一握の知力』 TopPage へ
『山之辺古文書庵』 総目次 へ
『味覚を問うは、国賊!』 目次へ
大阪では朝比奈隆さんと大阪フィルが

ベートーヴェン『交響曲第2番』
北ドイツ放送交響楽団(1960)
浦山桐郎監督の『キューポラのある街』

『キューポラのある街』(1962)
確か映画では、友人は曲名を言わなかったと思うが

"Johannes Brahms"(1833〜1897)
その指揮者の名は、ウィリス・ペィジさんと言い

”Willis Page”(1918〜2013)
当時大人気だったアメリカの医療現場ドラマ『ベン・ケーシ』の

"Vince Edwards"(1928〜1996)
『ベン・ケーシー』
オープニング
↑クリック