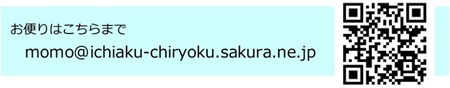一握の知力 > 山之辺古文書庵 > 味覚を問うは国賊 > 零 十七年後に書く前書き
零 十七年後に書く 前書き
標題『味覚を問うは、国賊』の意味について
私が音楽を聴くのは快楽を求めるからである。普段からよく聴くのはクラシックの楽曲であるが、古典的作品の〈崇高な精神〉に触れるために聴くのではない。ジャズも好んで聴くが、〈コアな趣味的興味〉を満たすために聴くのではない。いずれの場合でも〈気持ちよくなるために聴く〉のだ。
音楽を聴くのは快楽を求めるから …… と書きだして、思い出すことがある。小学校の音楽の授業である。『壱 ト長調の不思議』で触れているが、もう少し詳しく書く。
音楽と家庭科は専任の先生に教わった。少し年輩の女性であった。その先生には今でも感謝している。私は学校唱歌が好きで、日常のふとした折にその節(ふし)が口を衝いて出ることがある。今の時節なら、春は名のみの風の寒さや、の『早春賦』であろうか。半世紀を過ぎてもまだ褪せぬ芳香にしばし酔うことができるのは、その先生が唱歌の歌い方と聴き方をキチンと教えてくれたからである。
入学した頃の子どもでは、「叫ぶ」から、「話す」と「歌う」が分化していない。授業で長い時間をかけ、「話すこと」と「歌うこと」の技術習得が繰り返される。四年生の頃だったろうか、歌っていると、皆の歌声が空間ですうっと溶けあって、ああ今日はとても美しく歌えているな、と感じたことがあった。歌い終わったあとの余韻を今でも良く覚えている。しばらくの静寂のあと先生は、今日は本当に上手く歌えましたね、と感極まったように言われた。
しかし上手く歌えるようになったと言っても、授業で習った歌は、音楽室以外の場所では滅多に歌われることがなかった。普段は、大人が歌う流行歌を、例えば『別れの一本杉』とか『哀愁列車』などを歌っていたのだ。見よう見まねで歌うのだが、子どもなりに感情を込めて歌っていたし、歌うことの陶酔感もあった。ただ一つ不可解だったのは、うっとりとして歌っていても親は何とも言わないのに、来客があった時などに調子に乗ってそれを歌うと、たちまち「大人の歌うような歌をうたっていけません」とたしなめられることだった。親の、ちょっとマズイものを見られた、といった感じの狼狽ぶりに、こちらもすっかり動揺してしまう。
歌をうたうのは自由だが、過度に情感を表出してはならない。特に人前では慎むべきである。このような体験を何度かくり返して、少年は、世の中は「感情は包み隠せ」という道徳観で支配されていることを感じとったのである。
五年生の教科書に『ジングル・ベル』が載っていた。これは一つの驚きであった。なぜならこのような「普段から歌う歌」が、教科書に載ることはなかったからである。あの頃のクリスマスは「特別な日」であった。プレゼントがもらえ、ケーキが食べられる、なんていう日は、誕生日とこの日ぐらいのものだった。街に流れる『ジングル・ベル』は、いやが上にもザワザワとした期待感をあおり立てる。だから私たちは、授業では、慎ましやかに声を揃えて歌うというせっかく獲得した美質を忘れ、この「ザワザワとした期待感」に導かれるままに歌ったのである。お互いの期待感が共鳴しあって、歌声は次第に大きくなり、ワンワンと漆喰壁に反響しあった。歌い終えると、いやぁ、楽しかった、と児童たちは、お互いの上気した顔を見合わせた。初冬の寒さなのに額は汗ばんでいるし、息はまだ弾んでいる。だが、ざわつきが収まると、先生は冷ややかに言い放ったのである。
駄目です、今のような歌い方は駄目です。
先生は怒ってはいなかったし、苦笑しながらそう言ったのだけれど、一瞬にして児童たちは静まりかえった。あれほど盛り上がって歌ったのは初めての体験だったのに、それをアッサリと拒否された。何故か? 僕たちは何か、してはならないことをしたのだろうか? 集団が形成した高揚感は行き先を失い、気まずい沈黙のなかにのみ込まれていった。
このとき私たちは、表現の自由などと言われるものの、音楽表現は禁欲的な作法で縛られていることをはっきりと覚った。音楽をたしなむことは良いことだ。肉体に栄養が必要なように、それは精神の滋養である。だが、それは、あくまで精神活動の維持に不可欠な滋養なのであり、その摂取にさいして過度の快楽を求めるのは不作法である、いや、不道徳である!
音楽に限らず、歌舞音曲の表現者にならんとするなら、地道な訓練の積み重ねによる技能獲得が必要だ。ならば、観る、聴く、という享受する側に安住することを極め込むならば、まったくの〈素〉のままで良いのかといえば、けっしてそうではない。最低限の素養が備わってなければ〈表現の場〉に踏み入ることはできない。作家とその作品に対する〈共感〉にまで至りたいと欲するなら、先達たちの足跡を見極めてその道筋に分け入る覚悟がいる。古典とならばなおさらのことだ。
ところが、西洋古典音楽の道に踏み込んだ少年の前に立ち現れた先達たちは、とんでもない輩(やから)ばかりだった。中学校の音楽教師のことに関しては、本編に詳しく書いているので、そちらに譲るとして、雑誌・書籍・放送、などのメディアに生息していた専門家・評論家たちについて書いておこう。典型的なエピソードを一つ示せば良いだろう。
1960年代の半ばごろだったと思う、日曜の朝のラジオで音楽時評の番組があった。名を知られた専門家たちが、それぞれ聴いてきた演奏の感想・批評を述べ合う番組だ。得ることの出来る情報が極めて乏しかった時代である。私は熱心にその番組を聞いていた。ある時、モーツァルトの『フィガロの結婚』が名古屋弁で上演された、という話題で議論が交わされた。
ちょうど『てなもんや三度笠』に、もと『脱線トリオ』の南利明さんが鼠小僧役で出ていて、名古屋弁で笑いをとっていたころである。クラスの友人たちがその口まねをしていて、なるほど名古屋弁の〈けたたましい小気味よさ〉は大阪弁以上に喜劇向きだな、と感心したものだった。だから「名古屋弁のフィガロ」には大いに興味がそそられた。出演者たちが取っかえ引っかえ登場し、ドタバタ騒ぎをくり返す。確かに、フィガロと吉本新喜劇は同じような進行パターンじゃないか。これは面白そうだ。
先生たちがどのように批評するのか、固唾をのんでラジオに聴き入った。しかしまったく議論が弾まないのである。試みとしては評価すべきなんだろうが、チョットねぇ、……、といたような、歯切れの悪い込いコメントが交わされるばかり。しばらくすると、あそこが悪い、ここが気に入らない、という否定派の意見が出はじめて、次第に論難の雰囲気が支配的となり、最後にある評論家の次の一言でお終いになった。
フィガロに名古屋弁は合いません、駄目です、下品です。
私はあきれかえった。先生がたは、名古屋とフィガロの両方をおとしめている。さらに、正当な批評を聞きたいと願っている私の気持ちにも、冷や水を浴びせかけた。違うだろう、遠い過去に創られたものであっても、〈今〉と通じ合うからこそ〈古典〉なんだ。権威が公認した正統的解釈だけを信奉し、そこからの逸脱を非難するというやり方は間違っている。教条主義だ、と、社会科学を勉強しはじめていた私は憤慨した。
そもそも、公共の放送で、名古屋弁は下品だ、と言わねばならないほど、フィガロは、高貴でお上品な演目だろうか? まだまだ断片的な知識しか持っていない私であったが、フィガロはけっこう「きわどい路線をねらった」ものだ、というぐらいのことは理解していた。また、そのようなものとして聴かなければ、楽しめないじゃないか。
『フィガロの結婚』とはどんな話か。今さら、の感があるが、書いておこう。
色好みの伯爵(アルマヴィーヴァ)。いったんは「初夜権」の放棄を宣言したにもかかわらず、フィガロとの結婚を控えた小間使い(スザンナ)をものにしようとする。狙われたスザンナと伯爵夫人(ロジーナ)、それにフィガロが加わって、色仕掛けでもって伯爵に一泡吹かせるようとする。こんな話だ。それ以外にも、恋人がいるにも関わらず、女という女に興味をもって、恥じらうことなく愛慕の表現をする小姓(ケルビーノ)。借用証書を形にして実の息子との結婚をたくらむ女中頭(マルチェリーナ)。その他の登場人物が入り乱れての一日の話。だから、ボーマルシェの原題は『狂おしき一日、あるいはフィガロの結婚』。「狂おしき」とは "Folle" で、おそらく英語の "foolish" と近似の意味であろう。
なかでも極めつきは、ケルビーノが華奢な美少年という設定になっていること。スザンナとロジーナは、伯爵への反撃という渦中にあるのに、明らかにケルビーノに興味を抱いている! ケルビーノに女装をほどこして「あぁ、なんて可愛いんでしょう!」と、その身体をなでまわし、隙あらばこの美少年と二人っきりになろうと画策する。さらに、その美少年ケルビーノを女性が演じるわけだから、まさに不道徳の極み、性的倒錯の芳香がプンプン匂う。フィガロは、全編これ、素晴らしいアリアと重唱の連続なのだが、なかでも飛び抜けて人気があり、愛唱され、素人のど自慢でも歌われるのがケルビーノの二つのアリアであるのは、こういう成立事情があるからだ。
さあ、このオペラの、いったいどこが上品だと言うのか。
あらすじだけなぞれば〈下品〉、モーツァルトの美意識に共鳴すれば〈いき〉。フィガロとは、そんなオペラだ。しかるに、我が国の西洋古典音楽の先達たちは、後からやってくる我々がフィガロが描き出す快楽を享受すること、つまり〈いき〉の世界に魂を遊ばせることを妨げたのである。
彼らが、小市民的慎ましやかさから保守的になった、というのならまだしも、私には、彼らが戦前・戦中の意識構造をそのまま戦後まで持ち込んでいる、としか思えない。
作曲家の武満徹さんが書いている。戦争末期、勤労動員に駆り出された先で、学徒出陣で徴兵された士官候補生から『聴かせてよ愛の言葉を』を聴かされたことが、音楽体験の最初であったと。でも、大ぴらに聴いたのではない。彼らは、仲間内だけで、隠れて、そっと聴いたのである。黛敏郎さんも書いている。戦時中、音楽を勉強している、という理由だけで配属将校から殴られた、と。
振り袖を着て街を歩いていただけで、この非常時に不心得な、非國民! と罵られ、着物の袖をハサミで切り取られた。そんな時代だったんだ、過去の不幸な出来事だったのだ、で話を終わらせることはできない。
戦後、振り袖をちょん切られることはなくなった。どんな音楽でも堂々と聴くことが出来るようになった。音楽を勉強しても殴られことはなくなった。
だが、しかし、音楽で情念を解き放つことは、未だに許容されていないように思える。これはまさに、学校給食の、進駐軍支給の小麦粉や脱脂粉乳と類似である。それらはあくまで、栄養・滋養の摂取が目的。美味しくない、不味い、と不平を洩らすことは不道徳なのだ。
標題の『味覚を問うは、国賊』とは、このような意味である。
喰え、されど味わうな。これが我々戦後世代が受けた音楽教育の神髄であった。
これから読んでいただく全二十一章の作文は、そのような音楽環境のなかで、私がどのようにして西洋古典音楽を受容していったのかというプロセスの再現である。ビックリするような出来事が起こるわけでもない。退屈に思われるかもしれない。だが、当事者の私とすれば、けっっこうタフな体験であった。虚飾なく書いたつもりである。我々の世代がどのように自己形成をしていったのかという、一つの歴史的典型は示されていると思う。
この文章を書き始めた経緯については、『参 〈口上〉 この文章の由来』で述べているので、ここではくり返さない。
―― 零 十七年後に書く 前書き (了)
―― Page Top へ
―― 次章へ
◆◆◆ 2024/04/01 up ◆◆◆
『一握の知力』 TopPage へ
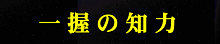
『山之辺古文書庵』 総目次 へ

『味覚を問うは、国賊!』 目次へ

今の時節なら、春は名のみの風の寒さや、

『早春賦』(歌)鮫島有美子
普段は、大人が歌う流行歌を、例えば『別れの一本杉』とか

『別れの一本杉』(歌)春日八郎
『哀愁列車』などを歌っていた

『哀愁列車』(歌)三橋美智也
ちょうど『てなもんや三度笠』に、

『てなもんや三度笠』
2:10ごろ、南利明さんが登場します
もと『脱線トリオ』の南利明さん

脱線トリオ(左から)
南利明、由利徹、八波むと志
ケルビーノの二つのアリアで

『自分で自分がわからない』
『恋とはどんなものかしら』
(歌)テレサ・ベルガンサ
Teresa Berganza
作曲家の武満徹さんが書いている

武満徹
士官候補生から『聴かせてよ愛の言葉を』を聴かされたこと

『聴かせてよ愛の言葉を』
(歌)リュシエンヌ・ボワイエ
Lucienne Boyer
黛敏郎さんも書いている

黛敏郎
『一握の知力』 TopPage へ
『山之辺古文書庵』 総目次 へ
『味覚を問うは、国賊!』 目次へ
今の時節なら、春は名のみの風の寒さや、

『早春賦』(歌)鮫島有美子
普段は、大人が歌う流行歌を、例えば『別れの一本杉』とか

『別れの一本杉』(歌)春日八郎
『哀愁列車』などを歌っていた

『哀愁列車』(歌)三橋美智也
ちょうど『てなもんや三度笠』に、

『てなもんや三度笠』
2:10ごろ、南利明さんが登場します
もと『脱線トリオ』の南利明さん

脱線トリオ(左から)
南利明、由利徹、八波むと志
ケルビーノの二つのアリアで

『自分で自分がわからない』
『恋とはどんなものかしら』
(歌)テレサ・ベルガンサ
Teresa Berganza
作曲家の武満徹さんが書いている

武満徹
士官候補生から『聴かせてよ愛の言葉を』を聴かされたこと

『聴かせてよ愛の言葉を』
(歌)リュシエンヌ・ボワイエ
Lucienne Boyer
黛敏郎さんも書いている

黛敏郎