映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。
何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?
今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。

髪長姫(ラプンツェル)

いばら姫
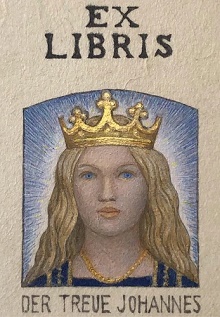
忠臣ヨハネス

絵姿女房
歌劇『オベロン』より

オベロンとティターニア

ファティメ(ファーティマ)
by
Lucia Elizabeth Bartolozzi-Vestris
(初演)
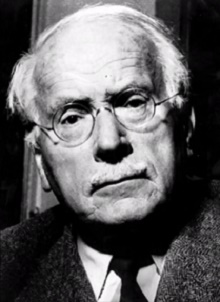
Carl Gustav Jung
(1875 - 1961)

河合隼雄
(1928 - 2007)

Carl Maria Friedrich Ernst
von Weber
(1786 - 1826)
ページの上段へ
“おとぎ話”としての『魔笛』
残された時間は短い。
じっくりとモーツァルトを聴こう。その8
2022/06/28
『魔笛』登場人物の人格にこだわる理由について
前回をこう締めくくった。
モーツァルトの場合は(ベートーヴェンとは)かなり違う。
確かに「15年前」という時間の隔たりはあるだろう。だが、それだけではない。
いわゆる「啓蒙専制君主」との関わりで、繰り返し失望を味わわされてきた彼は、フリーメーソンの一員として、その仲間から、新しい市民社会の思想を急激に取り込んでいたと想像できる。しかし彼はもう少し慎重だった。ベートーヴェンのように有頂天にはならなかった。新しい市民社会の全体像はまだまだ見通せない時代だったのに、その「市民社会が、詰まるところ、どこに行き着くか」をも予見していたように思える。真の天才の直感でもって。
もう一度、歌芝居『魔笛』の登場人物の人格を精査することで、モーツァルト、その人自身に迫ってみよう。懐古的趣味から言うのではない。これは極めて今日的な問題である。
いつまで『魔笛』の登場人物の“人格”にこだわるのだ、と言う人があるかもしれない。だか、書いたとおり、これは “極めて今日的な問題” なのだ。
我々は長い間「市民社会を順調に発展させ、豊富化させてゆけば、もしかすると全人類的な幸福が獲得できるかもしれない」という思いを大切に育んできた。現実世界は過酷と無慈悲の連続である。だからこそ、市民社会への幻想を、それが遂に幻想のまま終わるかもしれないと危惧しつつも、意識的あるいは無意識に心の拠り所としてきたように思える。だが今日、およその感じでいえば1980年代の終わり頃、つまり東西の冷戦構造が解体したあたりから、この市民社会の幸福感あふれるイメージの綻びが目立ちはじめてきた。そして今、市民社会は、貧困・格差・対立・憎悪・冷笑・無関心・孤立・その他、悪しき要素の数々で溢れかえっている。「市民社会的多様性と無秩序」が批判され、強力なリーダー出現への希求、強権的支配への傾斜、仮想敵を攻撃する狂信的大衆意識の囲い込み、などが保守主義者のイデオロギーとなり、大衆の多くがそれを共有するようなった。つまり、我々の多くは、ウラジミール・プーチンや習近平の暴挙を容認できないと口では言うが、実は、それを許している社会と同じ水準まで、自分たちの市民社会の劣化させてしまったのだ。
おっと、のっけからエンジン・ペダルを底までベタ踏みしてしまったようです。歳をとると、こらえ性がなくなり、短気になっていけません。最初に戻りましょう。モーツァルトは、「市民社会が、詰まるところ、どこに行き着くか」を予見していたように思える、という話でした。そのために、もう一度『魔笛』の登場人物の人格を精査しようとしていたのでした。
おとぎ話としての『魔笛』
ここまでで何度か“『魔笛』はおとぎ話である”と述べてきた。
「おとぎ話」とは「子供に聞かせる昔話。更に広く、童話。」(Oxford Languages)のこと。
あるいは「お伽噺」という漢字にこだわるなら「大名の話相手である御伽衆の手で整理・修飾された昔話のこと。」(百科事典マイペディア)となる。
おとぎ話という言葉には「非現実的な話。夢物語。」(Oxford Languages)という、派生的な「否定的」意味あいで使われることもあるが、ユング心理学や文化人類学を引き合いに出すまでもなく、おとぎ話・昔ばなしは「全人類に普遍的で、特に無意識のうちに行われている思考原理・行動原理の典型・類型をその基礎に含む」ことは、周知の事実である。
この観点から『魔笛』の登場人物の心理と行動原理を読み解いてみよう、と思う。「魔笛の謎」がさらに明らかにされるかもしれない、という期待を込めて。その方法は次の通り。いたってシンプルなものである。
『魔笛』の登場人物は、どこまで普遍的・一般的なおとぎ話・昔ばなしと同じで、どの地点からそれからずれて行くのか? 次の5つのおとぎ話の〔型(パターン)〕で検討してみる。
〔1〕:「幽閉されたお姫様」「眠り続けるお姫様」を救出するのは「他国の王子様」
〔2〕;「絵姿」に一目惚れ
〔3〕:「魔法のツール」の持つ効力
〔4〕:配偶者を得るための「試練」あるいは「謎かけ」
〔5〕:主人公の「影」としての他者
簡単に検討が済む場合もあれば、多少手こずる場合もあるだろう。今回は、〔1〕〔2〕〔3〕までを検討する。〔1〕〔2〕は簡単に済ますことができるが、〔3〕はなかなか手強いテーマだと予測できる。では、スタート。
〔1〕:「幽閉されたお姫様」・「眠り続けるお姫様」を救出するのは「他国の王子様」
おとぎ話では、幽閉されたお姫様を解き放つのは、他国からやってきた王子様である。
その例は、『心臓の無い巨人』、『黒いお姫さま』、『髪長姫(ラプンツェル)』など多数。
同様に、長い眠りにつく姫様を目覚めさせるのも、他国からやってきた王子様である。
例は『いばら姫(眠れる森の美女)』、『白雪姫』、など多数。
『魔笛』でも、幽閉されたパミーナの救出に向かうのは、他国からやってきた王子さまのタミーノであった。だからここはおとぎ話の定石どおり。
〔2〕;「絵姿」に一目惚れ
タミーノはパミーナの絵姿を見るなり一目惚れしてしまう。
現実の女性ではなくその「絵姿」を観て一目惚れする、というパターンは、グリム童話の『忠臣ヨハネス』を思い出させる。
死期を悟った王は、忠臣ヨハネスに、若き王子の後見を懇願するのだが、「黄金葺きの館の王女の絵すがた」のある部屋にだけは息子を入れてはならないと命じる。ヨハネスは亡き王の言いつけを充実に守ろうとする。だが、若き王は開かずの扉の部屋に執着して、無理矢理その部屋に押し入ってしまう。そして「黄金葺きの館の王女の絵すがた」を見るなり、失神してしまうのである。若い王は目覚めたとたん「あの美しい絵姿はいったい誰なのだ、恋しくて恋しくてたまらない、木々の木の葉がのこらず舌になろうとも、この恋心を言い表すことは出来ない」と言いだす。
河合隼雄さんは、この部分を次のように解析している。
すべての男性は心の奥の一室に一人の乙女の絵姿を持っていると言えるかもしれない。そして、その絵姿に似た女性に会うと心を揺さぶられ、それを追い求めようとする。このように男性の心のなかに存在する女性像をゲーテは「永遠の女性」と呼んだものと思われる。
ユングは男性の夢の中に登場する女性像のもつ深い意義に気づき、それを心、あるいは魂の像であると考えて、それらの像の元型となるものを仮定しアニマと名づけた。ユングのいう厳密な意味でのアニマは、無意識内に深く存在する元型としてわれわれは知ることができない。ただ、その元型がある文化や社会を背景とする個人の意識内にひとつのイメージとして刻印されるとき、われわれはそれをアニマ像として知ることができるだけである。だから、厳密に言えば、黄金葺きの館の王女の絵姿も、アニマ像のなかのひとつというべきであろう。王はそれを一目みるだけで気絶するほどに心をひかれる。つまり、それは王の魂を奪うものなのである。
(※)河合隼雄『昔話の深層』:講談社 p.175(初出:福音館書店)
ゲーテの「永遠の女性」という概念は分かりやすい。一方「アニマ」に関する記述は、ユング心理学に不案内な人にはいささか分かりづらいと思われる。少しだけ解説(のようなものを)付け加えておく。
「人間の普遍的無意識の内容のなかに、共通した基本的な型を見出すことができると考え、ユングは、それを元型と呼んだ」(※)。その「元型」の一つが「アニマ」である。「元型」は「普遍的無意識」のなかあるものを仮説的概念でもって想定しているものであるから、意識的言語によって、これだ! と限定して指し示すことができない。だから河合さんは、慎重に、若き王にとって黄金葺きの王女の絵姿は「アニマそのもの」ではなく、「その元型がある文化や社会を背景とする個人の意識内にひとつのイメージとして刻印され」たもの、無意識の領域から意識内に浮かび上がってきた「アニマ像のなかのひとつ」と表現しているわけである。
(※)河合隼雄『ユング心理学入門』:岩波書店:河合隼雄著作集 第1巻 p.60(初出:培風館)
『忠臣ヨハネス』の若き王の「一目惚れ」は、日本の『絵姿女房』を思い起こさせる。
美しい女房を眺めてばかりで、亭主(兵六と呼ばれる場合が多い)はいっこうに仕事に出かけて行こうとはしない。そこで女房は一計を案じる。自分の絵姿を持たせて、この絵を眺めて私がそばにいると思いなさい、と言うのだ。亭主はそれで納得して畑仕事に向かうのである。絵姿が先か、現実の女性が先かという差はあるけれど、この二つのエピソードの本質は変わらないと思う。
若き王や彦六が惚れているのは、現実の女性であると同時に「彼らの無意識領域に潜在していたアニマが、アニマ像として意識の中に浮上してきたもの」なのである。若き王や彦六の意識に浮上してきた「アニマ像」に裏打ちされているからこそ、現実の女性は一目惚れの対象となり得る。また、絵姿も「アニマ像」が具象化されたものであるからこそ、現実の女性と同等に、一目惚れの対象となり得るのである。
タミーノの場合も同じ。タミーノ自身が持つ「アニマ像」をパミーナの絵姿の中に見て一目惚れしてしまう。そして絵姿に一目惚れしてしまったおかげで、その後、さんざん艱難辛苦をなめさせられる。なぜなら、アニマ像は「《男》の魂を奪うものなの」であるのだから。
艱難辛苦の果てに物語がハッピー・エンドで結ばれるのも同じ展開である。
つまり、このタミーノの一目惚れも、おとぎ話の定石通りなのだ。
〔3〕:「魔法のツール」の持つ効力
前の2つの事例では、タミーノは普遍的なおとぎ話の通りにふるまっている。
だが、この事例〔3〕から、様相はいささか違ってくるように思える。
★ 三づくし ★
夜の女王は、パミーナの救出に向かうにあたって、タミーノとパパゲーノに魔法のツールを与える。これが「三づくし」になっていて、おとぎ話の定例どうりである。
a) 魔法のツールを手渡すのは「三人の侍女」。
b) 手渡されるツールは三つ。タミーノに「魔法の笛」、パパゲーノに「魔法の鈴」、そして「童子たち」。
c) 童子は三人。それに ……
d) タミーノが笛を吹くのが三回、パパゲーノが鈴を鳴らすのが三回、侍女が出現するのが三回、童子が出現するのが三回 …… 、だったらピタッと決まって嬉しいのだが、ここでは断言できません。ちょっと自信が無い。タミーノはパパゲーノとその存在を確かめ合うために幾度となく笛を吹いていたように思えるし、童子が出現する回数ももっと多かったように思える …… 、しかし今はこの文章を仕上げるのに精一杯、『魔笛』を通しで観て回数を確認する手間がとれません。悪しからず。
★ タミーノの笛とパパゲーノの鈴の、効能は薄い? ★
三回という数値はさておき、ここで確認したいことは、「タミーノの魔法の笛」と、「パパゲーノの魔法の鈴」の持つ効能と使われ方である。印象から入る話で恐縮するのだが、おとぎ話一般と比べて『魔笛』における「笛」と「鈴」は、いささかその効能が薄く、また、ここぞ! という場面では使われていないように感じられる。『魔笛』という題名にもなっているのに、肝心の「笛」の存在感が希薄なのである。明らかに、おとぎ話風リアリティの持つパワーから後退しているのではないか?
おとぎ話には、例を選ぶのに困るほど魔法のツールがちりばめられている。たいていは無欲で凡庸な人間として設定されている主人公が、絶妙のタイミングでこれらのツールを使って、身を守ったり、富を得たり、まれには元の木阿弥に戻ったりする。頭巾を被ると鳥や獣の会話が聞こえる。纏(まと)うと身体見えなくなる蓑(みの)は、燃えて灰になってもその効能を失わない。魔法のツールの使用が、お話を展開させるパワーとなっている。
舞台劇やオペラになると、魔法のツールは拡大・誇張されて表現され、その使用場面が、見どころ、聴かせどころ、になる。『魔笛』とよく似た設定で、同じような魔法のツールが使われるオペラがないか? 、と言うより、おとぎ話の定石どうりに魔法のツールが使われているオペラがないか? と探してみたら、ありました。少し時代は下るが、1826年初演の『オベロン』である。カール・マリア・フォン・ウェーバーの作。
★『オベロン』★
実は、よく演奏される序曲を除いて、私はまだこの『オベロン』を聴いた(観た)ことがない。まだ聴いたことのないオペラを引用するのは、はなはだ心苦しいのだが、『魔笛』と比較するのに好都合のよう思われるので、書物で得たあらすじだけを頼りに、このまま続けさせていただく。
歌劇の大詰め、レーツィアという女性と騎士ヒュオンが火炙りの刑に処せられることになる。いよいよ刑の執行、というタイミングで、騎士の従者シェラスミンが魔法の角笛を吹く。すると、あら不思議、その場の人たち全員が踊り出し、刑の執行は中断してしまう。さらに角笛を吹くと、妖精の王オベロンとその妻ティタニアが現れて、レーツィアとヒュオンは、これで試練は終わった、と告げられ、大団円を迎える …… 。
序曲だけなら You Tube に多数アップされているので聴いておきましょう。ハイティンク & ドレスデンの組み合わせのライブ録画である。
序曲の開始、ホルンのソロが、ニ長調で「ドーレ・ミー」という節を吹くが、これが従者シェラスミンの吹く魔法の角笛であろうか? アレグロが走り出すだすと、聞き覚えのある旋律が次々と出てきて、いやが上にもオペラ本編への期待をもり立てる。
さて、『魔笛』と『オベロン』の比較である。
主人公たちが「試練」をくぐり抜けなければならぬこと、主人公たちが魔法の笛(角笛)所持していること、これは両者に共通である。
『オベロン』の場合は、歌劇のクライマックス、主人公が火炙りの刑に処せられるという絶体絶命の場面で、待ってました! とばかり角笛が吹き鳴らされ、一瞬にして万事がめでたく解決する。魔法の角笛が物語を動かし、ハッピーエンドを導くのだ。まさに起死回生の一吹き、いや、二吹きか。
これに比べると『魔笛』における「魔法の笛」と「魔法の鈴」の使われ方は、いたって慎ましやかである。笛と鈴が使われなくとも物語の進行には大きな齟齬をきたさないのでは、と思わせるほどである。それでは実際に笛と鈴が最初に使われる場面を確認しておこう。
★ タミーノはいつ、何のために笛を吹くか? ★
第一幕のフィナーレ、三人の童子(何故か宙に浮いている)に導かれて、タミーノはパミーナが監禁されているらしい寺院の前にやってくる。寺院には三つの扉がある。(また、三つ、だ!)
タミーノは最初に、右側の "Tempel der Vernunft"(理性の寺院) と書かれた扉から中へ入ろうとする。すると寺院の中から "zuruck!"(下がれ!) と僧侶たちが唱和する声が響く。タミーノは次に、左側の "Tempel der Natur"(自然の寺院) と書かれた扉へ向かうが、またしても "zuruck!"。そこで中央の "Tempel der Weisheit"(叡智の寺院) に向かう。
ここまでなら観客は納得して劇の進行を観ていられる。現実から遊離した理屈ではダメ、さりとて脳天気な自然回帰でもダメ、選ぶべきは "Weisheit"(叡智)である、とはいかにも啓蒙主義集団であるザラストロのスローガンに相応しい。
だが、タミーノがその叡智の扉に向かうと、扉が開いて、位の高そうな僧侶が出てくる。リブレットには "Sprecher"(弁者) と書かれている。代表者・スポークスマン・広報担当、といったあたりであろうか。この弁者がくせ者である。苛つかされること甚だしい。タミーノの真摯な問いかけにまともに答えない。のらりくらりと混ぜ返すばかりである。その極めつきが次の問答であろう。
タミーノ:パミーナは元気でいるのか? まだ生きているのか?
弁者 :それに答えることは許されていない。
タミーノ:何故だ、その理由を聞かせてくれ。
弁者 :まだ言えない。黙すことが私の義務なのだ。
弁者の言動は、完全に「いたぶり」であり「いじめ」である。叡智からはとんでもなくかけ離れた行為である。もしこれが、タミーノでなく八尾の朝吉なら、いや、朝吉親分でなくとも関西在住の平均的男性なら、ええ加減にせぇよ、パミーナは生きとんのか、死んでしもぅたんか、どっちやねん、はっきりせえ、これ以上ぐずぐずぬかしたら、しばきまわすぞ、われぇ、と怒鳴り散らすところである。
そう、「しばきまわすぞ、われぇ!」で正解なのだ。なぜなら、論理的言語での意思疎通が“通信障害”に陥った状態なのだから、その障害から回復するには「何か別の力の行使」が必要となる。
タミーノは王子であるから、関西の平均的男性のように振る舞うわけにはいかないだろう。でもちょっと待ちたまへ。タミーノ君、君は「魔法の笛」という「別の力」を保持しているではなかったか? 何故、ここでそれを使わないのだ?
タミーノが、ピーヒャラ・ヒャラリと笛を吹く。すると弁者はたちまちひれ伏して、タミーノに道をゆずる、タミーノは堂々と叡智の扉から寺院の中に母いって行く …… 、おとぎ話なら、こんな風に話が進むはずである。
しかしタミーノは笛を吹かない。弁者は禅問答のような台詞を吐いて寺院の中に消えてしまう。一人取り残されたタミーノ。それでも彼は問答を続ける。寺院の中から、僧侶たちの声が返ってくる。タミーノが、パミーナはまだ生きているのか? と嘆きの言葉を発する。僧侶たちは、あまりにもタミーノが可哀想だと思ったのか、パミーナは生きている、と返してくる。この声でタミーノは少し元気を取り戻す。
この時である、タミーノが魔法の笛を取り出すのは! 彼は、感謝の音を吹き鳴らそう、と言って笛を吹き始める。
この点が大事なポイントである。
魔法の笛は、その魔力でもって、その奏者に超人的な力を授けることを止めている。また邪魔だてする敵対者を退けたりもしない。タミーノは、理不尽な苦難をなめさせられたすえ絶望の淵に落ちこみ、そこでわずかな希望を見出す。その感謝の気落ちを笛の音色に託すのである。この時、笛はすでに「魔法の笛」ではなくなっていて、タミーノの心に感応しそれを表現する「モーツァルトの笛」に立ち戻っている。
★ パパゲーノはいつ、何のために鈴を鳴らすか? ★
ここから先は、ユーモラスであると同時に極めて感動的である。笛の音に誘われて動物たちが続々と出現し、タミーノの周りで戯れはじめる。そして、このタミーノの笛の音をききつけて、パパゲーノが笛の音を返してよこす。タミーノは、パパゲーノはすでにパミーナに出会ったのだろう、と確信し、このまま笛と笛で交信してゆけば、きっと二人に出会えるはずだ、と歩み始める。
さて、こちらは、パパゲーノとパミーナ。タミーノの笛の音を聞いて、さあ行きましょうと励まし合う。ところがそこへ、モノスタートスが大勢の部下を引き連れて登場。やっと見つけたぞと、たちまちパミーナを縛り上げてしまう。
この時とったパパゲーノの行動はタミーノより賢明であった。彼はまだおとぎ話の世界にしっかりと踏みとどまっていて、魔法の鈴をとりだしてかき鳴らす。
するとどうだろう、あら不思議、モノスタートスとその部下たちは、タミーノを縛り上げることを止め、こんな美しい音は聞いたことがない、と踊り出すのである。
モーツァルトの書いた音楽のなかでも、この部分は最上ものである。断言してよい。
『魔笛』はもう何回聴いてきたかしれが、この場面になると、私は幸福感に満たされて感涙にむせんでしまう。タミーノの場合と少し異なって、パパゲーノは、おとぎ話の世界に留まったまま、モーツアルト音楽の最良の具現者に化身している。
しかし不思議だ。パパゲーノの魔法の鈴は、実際の演奏ではチェレスタで弾かれているわけだが、ト長調で、ソファミ・ミ・ミ、という下降音型で始まる極めてシンプルなもの。歌の伴奏になっても(手元に楽譜がないし、音楽の専門家でもないので、断定的なことは言えないが)主和音と属和音を交互にかき鳴らすだけ。それが、何故、これほどの幸福感をもららすのか!
少し長くなるが、タミーノが寺院の前に到着してから、パパゲーノが魔法の鈴を鳴らしてモノスタートスを踊らせるあたりまでを通して聴いていただきたい。引用する
YouTube の動画は、以前に引用したのと同じ、レヴァイン & メトロポリタンの実況録画。
タミーノが寺院前に到着する(49:20)あたりから再生が始まるように埋め込んである。
タミーノがパミーナの生存を知って感謝の笛を吹くのは(56:25)あたり、
モノスタートスとその手下が出現してパミーナを拘束するのは(1:00:40)あたりである。
★ 大急ぎでまとめを ★
タミーノの「魔法の笛」とパパゲーノの「魔法の鈴」は、おとぎ話の決まり事としての効力をなかば喪失している。端的に言うならば、窮地を脱するための起死回生のツールとして、あるいは眼前の敵を倒すためには使用されない。
タミーノの笛が吹かれるのは、自分の幸福感を表現するとき、仲間の存在を確かめ合うため、あるいは、試練をくぐり抜けるとき自分自身を励ますため、これらの場合に限られる。
パパゲーノは、第二幕で二回鈴を鳴らす。それによってパパゲーナが出現する。いわば愛の場面にむかうための媚薬としてそれは働いている。
それならば第一幕のモノスタートスに対する使用はどうなのだ、敵を倒すために使用しているではないか、と反論する人がいるかもしれない。だが、よく考えていただきたい。パパケーの鈴は、モノスタートスを退けるために鳴らされるのではない。鈴の音は、モノスタートスとその手下たちの「歌心」に訴えかけて、女人を束縛するというような蛮行を忘れさせたのだ。その証拠に、モノスタートスとその手下たちは、なんて素敵な響き! こんなものは見たことも聞いたこともない、と驚喜して踊りまくるのである。タミーノの笛の音に惹かれて動物たちが出現し戯れるのと同じ効能である。
もう気づかれている方も多いだろう。タミーノの笛も、パパゲーノの鈴も、「歌心」で同化しうる仲間に対してだけ奏でられる。ザラストロとその集団の人たちに対しては、タミーノの笛が吹かれることも、パパゲーノの鈴がかき鳴らされることも、絶対にあり得ないのだ。
冒頭で、モーツァルトは「市民社会が、詰まるところ、どこに行き着くか」を予見していたのでないか、と書いた。そう、啓蒙主義・近代合理主義がもたらす社会は、その根本において、歌心を喪失させる世界になるのではないか、とモーツァルトは直感していたのだと思われる。
周りを見回していただきたい。幸運にも「勝ち組」「上級国民」に属することができたという人々が、詰まるところ「社畜」としての日常を強いられ、幸福感ある食卓、子供の養育、歌舞音曲の楽しみ、草花の香り、鳥たちのさえずり等々、人間を人間たらしめる幾多の楽しみから離脱させられている、この現状を。また、すでに多数派となった「底辺層」が、パッケージで俗悪な粉飾を施された粗悪な大量生産品で、何とか糊口を凌いでいるこの現状を。「上級国民」であれ「底辺層」であれ、その楽しみとして差し出されているのは、ステルス・マーケティングで裏打ちされた、ド派手な色彩と、音響を辺り構わずまき散らされる騒音でしかない、という現状を。
モーツァルトは、ザラストロとその教団が創ろうとしていた組織集団に、このような近代市民社会形成の萌芽を見ていたのではなかったか。
思いつきで、そう言うのではない。今回検討できなかったおとぎ話のパターンのあと二つ、
〔4〕:配偶者を得るための「試練」あるいは「謎かけ」
〔5〕:主人公の「影」としての他者
この二つが『魔笛』においてどのように変容をうけているかを検討すれば、それは、さらに明確になるはずである。
ページの上段へ
−−【その8】了−−
残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ