映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。
何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?
今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。
これが昔の『岩波文庫』
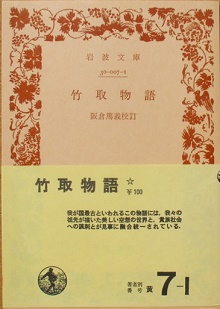
薄い半透明のカバーがついていた。パラフィン紙と呼んでいたが、今でも正式名は知らない。
日本文学は「黄」、海外文学は「赤」、思想書は「青」、社会学書は「白」、それに少し後になってからだと思うのだが現代日本文学のシリーズが始まって「緑」の帯が着いていた。それが書店の棚に整然と並んでいる姿は、とても美しくかった。独特の匂いもした。
これが今の『岩波文庫』

ビニールでコーティングした派手なカバーが付くようになったのは、1960年代の終わり頃か、角川文庫の横溝正史シリーズあたりからではなかったか?
各社がそれに追随するようになり、最後までこらえていた岩波もカバーを付けるようになった。
本はその「背」の姿で購買欲がそそられるものだ。おかげで今の文庫版売り場は雑然と汚ならしくなってしまった。ベストセラーの平積みで儲けようとする下品な根性が、出版文化を劣化させた一因でもあると思わないのだろうか。
仕掛けたのは誰だ? たぶん角川春樹だろう。もし間違っていても謝罪する気は無い。
『源氏物語』には「物語の出で来はじめの祖なる竹取の翁」として『竹取物語』のことが出てくる。
その頃すでに「さし絵」も存在していたらしい。
だが『竹取物語 絵巻』はあまり多く現存せず、あっても江戸時代の写本なんだそうです。
立教大学には、そのうちの一つが保管されていて、
ネット上にも
竹取物語絵巻 デジタルライブラリ
として公開されています。
ぜひ、ごらんになってください。
『竹取物語 絵巻』の他
『竹取物語 貼交屏風』も掲載されています。
どの絵も自由にダウンロードできるように設定されているので、
今回引用したエピソードに相当する部分を切りぬいて利用させていただきました。
かぐや姫の求婚者たち
最終候補として残った
五人の〈やんごとなき〉男たち

№1 石作皇子
姫の前に差し出された赤い袋の中身が「仏の御石の鉢」
中身は大和の古寺にあった「おびんずる」のもの。

№2 車持皇子
精巧に作られた「蓬莱の玉の枝」のレプリカを差し出す。
これに、姫も翁も一瞬はだまされてしまう。

職工たちが、まだ代金をいただいておりませんと、訴状を持って来て、贋作であることがバレる。

№3 右大臣阿倍御主人
王さんが探したという「火鼠の皮衣」が、唐から到着。

試みに、火にくべると
いともあっさり
「めらめらと焼けぬ」

№4 大納言大伴御行
この男のパワハラ的人事管理は、今でいうブラック企業なみ。
「天の使といはむ者は、命を捨てても、おのが君の仰せ言をば、かなへむとこそ思ふべけれ」
「この珠取り得では、家に帰り来な」

大納言、自らドラゴン探し。
「筑紫の方の海」で大嵐に襲われる。
龍と雷がお怒りなのだ、お許しください、二度としませんから!

№5 中納言石上麻呂
だんな、「燕の子安貝」を手に入れには作戦が必要ですよ。あんな、騒々しいやり方じゃ、ダメですぜ。

「平めるもの」があったぞ、
それ下ろせ!
綱がプツン!
中納言落下!

ページの上段へ
“おとぎ話” の 変容
残された時間は短い。
じっくりとモーツァルトを聴こう。その9
2022/08/28
モーツァルト論考 中間総括
新規原稿のアップが大巾に遅れてしまいました。申し訳ありません。本音を申せば、私の新稿を待ちわびている人などまずいないだろうと確信しているのですが、もし、たった一人でもおられたら、その貴方(貴女だったら、もっと嬉しい)に対して、心からお詫び申し上げます。
モーツァルトに関する連載も今回で9回目。それに間合いも空きすぎました。この論考が、どこからスタートし、今どのあたりに居て、これから先どこに向かっているのか、ともすれば書いている本人も道筋を見失いそうになります。ここらで一度、中間総括のようなものを書いおくのが良いと思います。
私は西洋古典音楽の愛好家です。中でもモーツァルトは、私にとって《特別なもの》です。そしておそらく、西洋古典音楽を愛する多くの人にとっても、モーツァルトは《特別なもの》であるに違いありません。
モーツァルトについての論考や感想の表現は、世の中にそれこそ星の数ほど散在しています。それに、誰も気付かないような星屑の一つを付け加えることに、何か意味があるのか …… ? あります。私の論考は、誰に何と言われようと、あるいは、誰も気にかけてくれなくとも、私独自のもの。今のところ歌芝居『魔笛』の解析に終始していますが、この一連の論考は、おそらく今までに為されたことのない論点を提示している、という自負心を持っています。
これは音楽に関する論考です。しかし執筆にあたっては、音楽とか音楽史の専門家が書かれたものはほとんど参考にしていません。と言うより参考にならなかった。モーツァルトの謎を解くチカラを何も与えてくれなかった。私がより所としたのは、次の三つの思索的営為です。これらは文章のなかで、はっきりと《出典》として明記しておきました。
1: 文化人類学と網野善彦歴史学
2: 上野千鶴子さんに教えていただいたフェミニズムの考え方
3: 河合隼雄さんに教えていただいたユング心理学の考え方
今後の展開においては、これに加えて、澁澤龍彦さん・種村季弘さんの著作に大きく依存することになると思います。いわゆる近代・啓蒙主義に対する《異端の肖像》を見極めるために。
えっ、近代・啓蒙主義に対する《異端》って何?
結論を先走りして述べるなら、近代・啓蒙主義とは「社会がこうあるべきと示した規範を遵守して、ノーマルな人間であることを強要する」時代です。モーツァルトの音楽はその強要から自由になろうとする精神の躍動である、という風に私には聴こえます。もちろん、モーツァルト自身は、そのようなことは、これっぽっちも考えていなかったでしょう。彼は音楽で人の心を沸き立たせることしか考えていなかった。
でも、その音楽はどこまでも自由。何かから自由になろうとする限定的なものではなく、絶対的な自由。耳に心地良くすんなりと精神に染みいるよう聴こえますが、モーツァルトの音楽は、カゲキに申せば、近代・啓蒙主義を批判的に対象化するのです。
だから《異端》の実像を確かめてみる必要がある。モーツァルトは、それらの《異端》とどのように関わっていたのか? いや、モーツァルト自身が《異端》であったはずなのだ。それも《普遍性にまで昇華された異端》として。
先ほど音楽の専門家の著作は参考にできなかった、と述べましたが、一点だけ例外があります。
今回、自分なりのモーツアルト論考を書いてみよう、と心が動いたのは、その論考を読んだからです。それは、
アッティラ・チャンパイ 『 《魔笛》の秘密、あるいは啓蒙主義の帰結 』
音楽之友社から出ている『名作オペラブックス』は、ほとんどこのアッティラさんが編集したシリーズを翻訳したもののようです。その『名作オペラブックス 5 モーツァルト 魔笛』では、アッティラさん自身が巻頭論文を書いています。それが『《魔笛》の秘密、あるいは啓蒙主義の帰結』です。
歌芝居『魔笛』の上演では、台詞部分に大幅な省略がなされるのが通例です。オットー・クレンペラーの録音などは、台詞はすべてカットされている! でも、充分に慣れ親しんだ楽曲ですから、ふつう鑑賞するにあたってそれは大きな瑕疵にはなりません。
しかし『魔笛』を作品として解析し、作者の制作意図を正確に把握しようとするなら、それでは具合が悪いだろう。そこで、省略の無い台本を求めて『名作オペラブックス 5 モーツァルト 魔笛』を図書館から借りだしました。その巻頭に見つけたのがこの論文です。
この論考が素晴らしかった!
ひと言で言えば、これまでの魔笛論はすべて「こんなに酷いでたらめな台本を、なぜモーツアルトは容認したのか」という「天才に対する擁護論」に終始してるように思えます。その理由として、彼の病の進行だとか、経済的困窮とか、フリーメイスンの教義の取り込みだとかが、入れ替わり立ち替わり引き合いに出されてきました。 …… だから、天才としてもやむを得なかったのだ、という具合に。これって、贔屓の引き倒し、というやつでしょう。まぁ、多少は事実の上面をなぞってはいるでしょうが、「魔笛は、一聴して台本に不整合があるように思えるのに、何故これほどまでに我々を魅了するのか」という《魔笛の謎》には、いささかも接近していない。このような魔笛論考史に、『《魔笛》の秘密、あるいは啓蒙主義の帰結』は、みごとに引導を渡した、と断言して良いでしょう。
私は、モーツァルトについてあれこれと考えてきました。『魔笛』に関しても、私なりの解析イメージを育んでいます。しかし、如何せん、自分は西洋古典音楽の平凡な愛好家にすぎない。こんな解析をしてみたけれど、凡百の好事家の独りよがりではないのか、専門家からみれば、笑止千万、とんでもない間違いを犯しているのではないか …… 、と言う自戒の念に囚われていました。言語化してみたところで、鼻の先で笑い飛ばされるだけのことではなかろうか? こんな思いから、それを言語化するのをためらっていました。
その時出会ったのが、アッティラ・チャンパイさんの『《魔笛》の秘密、あるいは啓蒙主義の帰結』でした。おぉ、音楽の専門家が、私が抱いていた魔笛のイメージとほぼ一致する内容を、見事に解析し言語化しているではないか!
こういう次第で、アッティラさんの論文に背中を押される形で、『魔笛』の論考を書き始めたわけです。モーツァルトが目前に見据えながら、そっくりそのまま受け入れることにためらいを感じていた新しい社会理念の形態を「啓蒙主義」と呼ぶのは、この論文からの借用です。もちろん、内容のすべてがアッティラさんからの借用ではありません。私が主に依存しその考えを活用したのは、先に述べたように、個人名で限定すれば、網野善彦・上野千鶴子・河合隼雄の三氏。今後、依存することになるのは、澁澤龍彦・種村季弘のお二人です。
これで、私のネタばらし、格好をつけていうなら「思想的背景」を明らかにしました。さあ、読者の貴方と貴女。いっしょに、モーツァルトを考えて行きましょう。貴方(貴女)の貴重な時間を、決して無駄にはさせません。
さて、本筋にもどりましょう。
歌芝居『魔笛』を「おとぎ話」として解析する、というテーマまで来て、その途中で中断していたのでした。
【注】アッティラ・チャンパイさんに関しては、その名前から推してハンガリー出身ではないかと思っていたのですが、彼がどこでどのような仕事をしてきた音楽学者なのか、ほとんど情報を得ることができません。検索で唯一ヒットしたのが、"WikipediA" の "Attila Csampai" の項目。ただし独語のみ。でも、"google chrome" でアクセスすれば、翻訳機能を使ってかなり正確な日本語訳で読めます。お試しください。
『魔笛』を「おとぎ話」として考えなおすことの意味
『魔笛』の登場人物は、どこまで一般的なおとぎ話・昔ばなしの定石=お約束の通りに振る舞っているか? どの地点から定石からずれて行くのか?
なぜこのような作業をするのかと言えば、解釈・解説が入り乱れている「謎だらけの魔笛」の主題が、この点検作業でスッキリと明確になるのではないか、と期待するからである。
一般的なおとぎ話から5つの〔型(パターン)〕を選んだ。前回、3つのパターンを検討した。残りは2つ。結論を先に述べてしまうことになるが、まとめると次のようになる。
〔前回に検討したパターン〕
1;「幽閉されたお姫様」・「眠り続けるお姫様」を救出するのは「他国の王子様」
→ 定石どおり。
2;「絵姿」に一目惚れ → 定石どおり。
3:「魔法のツール」の持つ効力 → 定石から大きく逸脱している。
〔今から検討するパターン〕
4:配偶者を得るための「試練」あるいは「謎かけ」 →定石から大きく逸脱している。
5:主人公の「影」としての他者 →定石から大きく逸脱している。
では、さっそく、残りの「4」「5」にとりかかろう。
でも今回は、話が横に膨らみすぎて、「4」だけしか掲載できませんでした。
まぁ、良いか。別に急ぐ旅でもないし。
配偶者を得るための「試練」
美しく賢明な娘(横暴な王女様の場合もある)には、我こそ娘を(姫を)ものにせん! という求婚者が殺到する。求婚者に対して娘は、承諾を与えることも拒絶することもしない。その代わり娘は、これら数多の求婚者に対し「試練」を与えて、これを全うした男なら求婚に応じても良いと言い渡す。それらの試練は、近代合理主義的観点から見ると、およそ達成不可能に思えるような類いのもので、そもそも娘は「結婚したくない」のではないかと疑わざるを得ない。娘を手放したくない親の心を代弁しているのかもしれない。実際、娘の代わりに親が「試練」を出題するパターンもある。すべての求婚者は、例外なく、この「試練」を達成してみますと勢い込む。その達成には多くの危険 ― 死に至る場合もある ― が伴うにもかかわらず。
東西を問わず、この求婚者に試練を与えるというパターンの話は極めて多い。おとぎ話の何割かはこのパターンではなかろうか。我々がすぐに思い浮かべるのは、「物語の出で来はじめの祖なる竹取の翁」のかぐや姫であろう。『竹取物語』は、初心者にも読みやすい古典として、高校の古典の教科書にも採用されているから、原文に親しまれた方も多いだろう。岩波文庫だって「★一つ」、手軽に手に入った。今も販売されているが、光沢のあるカバーがついて値段が10倍になってますね。
かぐや姫が求婚者に与える試練の内容を振り返っておこう。理屈だけ述べて先に進んだのでは遊びごころが不足、モーツァルトを語るにふさわしい作法とは言えないだろう。
幾多の男たちが姫に近づこうと試みる。家の周りをうろついたり、のぞき見したり、垣根に穴を掘ったりして。これらストーカー的行為で姫に近づこうとする者たちはことごとく退けられ、最終候補として残ったのは、止んごとなき公達の五人。さて、
かぐや姫と婚約するための試練 五つのエピソード
★★ エントリー・ナンバー_1 石作皇子(いしづくりのみこ) ★★
求婚に応じる条件として石作皇子に与えられた試練は、お釈迦様が使われていた「仏の御石の鉢」を手に入れて来い、というもの。まさに無理難題。
世はまだ「遣唐使」の時代。この国家的プロジェクトのため、中央政府幹部候補のエリートたちが命がけで船(まだ舟と表記すべきか?)に乗り込んでいた。嵐に遭わず、座礁・難破もまぬがれるという幸運に恵まれた場合、やっとこさ唐の東海岸のどこかに漂着できた。
あの弘法大師・空海だって、 803年におそらく難波の津を出立したのだが神戸沖で早々と難破。それに懲りてか翌年は博多から出発。一月半かけてやっと福州に到着(漂着か?)。目的地は長安(今の西安)だから、方角としては南に45度ずれてます。もちろん地元の役人は、倭国(この頃から「日本」と名乗るようになったらしいが)から使者が来るかもしれない、なんてことは知らされていないから、中央政府との連絡やら何やらで一ヶ月もその場で足止め。この時、ことが穏便に進んだのは空海が現地の言葉を喋れたから、というのは司馬遼太郎さんの『空海の風景』から得た知識。おそらく司馬遼さんも多くの空想を交えて執筆していたはず。正月に西安で皇帝に謁見という当初の予定にぎりぎりセーフで間に合った、と言う。
そんな時代に、唐・西域はおろか天竺まで行ってこい、と言うのである。
石作皇子は、天竺まで往復すれば相当の時間がかかるだろうと考え、三年間姿をくらませたあと、
「大和国十市郡」の古寺の賓頭盧(びんずる)様の前にあった石鉢にチョコチョコと細工をして、ハイ、これでございます、と持参する。かぐや姫は最初から疑ってかかっていて「光あるやと見るに、蛍ばかりの光だになし」で、たちまち嘘がばれる。
ちょっと調べてみたのだが、「大和国十市郡」とは、今の奈良盆地の中央から南のあたり。何だ、今の私が住んでいるあたりじゃないか! 都が京に遷ってさほどの時も経っていないのに、すでに大和のこのあたりはオワコン扱いされてます。悲しい限りである。
★★ エントリー・ナンバー_2 車持皇子(くらもちのみこ) ★★
車持皇子に与えられた試練は、「蓬莱の玉の枝」を取ってこい、というもの。「蓬莱」といっても、「大阪ナンバ551の蓬莱」じゃないよ。東方はるか海上にあって仙人たちが住むと言われる桃源郷のような所。西の次は東。かぐやのお姫様は、男どもを文字通り東奔西走させることに加虐的な快感を覚えるらしい。
石作皇子が凡庸・素朴、極めて単純な手口でかぐや姫をだまそうとしたのに対し、この車持皇子はなかなかの策士。前例の失敗から学んだのだろう、一度は難波から船出をし、数日後密かに舞い戻る。全国から名人・上手といわれている六人の鍛冶職人(英語でいうなら、Goldsmith か)を呼び寄せて、秘密のアジトに籠もらせて贋作を造らせる。千日かけて作品は完成。そして、やっと難波に戻ってきました、という芝居を打つ。
差し出されたレプリカは、さすが匠(たくみ)たちを集めて造らせたことだけあって見事な出来映え。この蓬莱の玉の枝を手に入んとて、艱難辛苦は幾ばかり、とその冒険譚まで披露する。これにはかぐや姫も翁もすっかりだまされ、姫はこの男の嫁になるしかないのかと観念し、翁は寝所の用意まで始める。ところが間一髪、六人の匠たちが、代金をまだ払って貰っていないのだが、と押しかけて来てウソがバレる。
★★ エントリー・ナンバー_3 右大臣阿倍御主人(うだいじんあべのみうし) ★★
右大臣阿倍御主人に要求されたのは「火鼠の皮衣」(ひねずみのかわごろも)。唐土(もろこし)にあると伝わる宝物。火中に投じても燃えず、汚れだけが燃え落ちてそれが光りを放つ、という優れもの。
右大臣は大金持ちの家系。(某)友作氏やイーロン(某)氏のように何事も多額の金銭で解決しようとする男。信用できる使いの者に大金を持たせて唐に送り、何とか「火鼠の皮衣」が手に入らぬかと、王慶さんに持ちかける。使いの者は確かに「火鼠の皮衣」を持って唐の船で帰って来る。ワンさんは、こう言ったという。
いやあ苦労しましたよ、むかし天竺の僧が唐に持ち込んだものが西方の山寺にあると聞きました、そこで朝廷に許可をとってから、西方の地方役人とかけ合って、やっと手に入れました。お預かりした金額では足らぬと云うので、五十両たてかえておきました。五十両の支払いが出来ないというのなら「火鼠の皮衣」を返していただきたい。
右大臣は、大金をつぎ込んでいい女を口説くという、成金御曹司型プレーボーイの元祖なのだろう、いかにも怪しげな中国人のワンさんにコロリとだまされてしまう。ただし、現在の(某)友作氏がだまされたのどうか、私は知らない。
かぐや姫のもとに持ち込むと、姫は、燃やしてみましょう、本物なら燃えないはず、と言う。右大臣は本物だと信じ切っているから、それなら、さあ、さあ、燃やしてみてください、と自身満々。ところが、この「火鼠の皮衣」、いともあっさり「めらめらと焼けぬ」。「大臣、これを見給ひて、顔は草の葉の色にて居給へり」。これまでの話は求婚者がかぐや姫をだまそうとするものであったが、今度は、求婚者自身がだまされる側に回っている。
ちなみに、「火鼠の皮衣」とは石綿(アスベスト)のことではないか、という説があるらしい。実際に「火浣布」という名で実在していたものだそうだ。
★★ エントリー・ナンバー_4 大納言大伴御行(だいなごんおおとものみゆき) ★★
大納言大伴御行への要求は「龍(たつ)の頸(くび)の玉」。五編のお宝探索譚のうち、このエピソードが一番起伏に富んでいて面白いと思う。大納言はかぐや姫をだまそうとはしないし、大納言がだまされることもない。ただし、体育会系直情径行型男性の恋愛成就がいかに困難であるかを、如実に語るエピソードであろう。
大納言は配下の者に「龍の頸の玉」を手に入れてこい! と命じる。「天の使といはむ者は、命を捨てても、おのが君の仰せ言をば、かなへむとこそ思ふべけれ」と強権的パワハラを行使。「この人々の道の糧、食ひ物に、殿の内の絹、綿、銭など、あるかぎり取り出でて」と懐柔策にも怠りない。さらに、お前たちが帰るまで私は「斎ひ(いわひ・いもひ)をして」、つまり、身心を清め不浄を避ける生活をするから、お前たちは「この珠取り得では、家に帰り来な」と命じる。ほとんど、現代日本企業の経営スタイルと同じですね。そう言えば一昔前、植木等さんが「千年以上の昔の親父がぁ~」と唄っていましたっけ。
配下の者は、そんなこと言ったって無理なものは無理だもんね、だいいち龍を探すたって何処へ行けばいいんだ、と口々に言い合ってそのまま雲隠れ。一方、大納言の入れ込みようは大変なもので、かぐや姫を迎え入れるのだからと屋敷じゅうをピカピカにリメイク、正室やお妾さんたちとは全員と離縁。さて、準備万端、配下の者の帰還を今か今かと待ちわびるのだが、いっこうに帰ってくる気配がない。しびれを切らして難波(なにわ)の浜まで忍んで行き、あれこれと尋ねまわるのだが、龍を捕まえる? そんなヤバイ仕事を引き受ける船なんかあるもんか、という答えが返ってくるばかりで一向に埒があかない。そこで「わが弓の力は、龍あらば、ふと射殺して、頸の珠はとりむ」と自分で船出することを決心。自分の能力を過大評価しすぎるのも、このタイプの男にありがちなこと。そして、あちこちの海を探索して「筑紫の方の海」までというから、玄界灘あたりまで行ったらしい。
ところが大嵐に翻弄され船は操縦不能となる。このままだと、沈没するか、雷に打たれて炎上するか、運良く逃れても漂着する先は南海の孤島でしょう、と老練な船長(船頭か?)も弱音を吐く。こんな目に遭うのも貴方が龍を殺そうとなさったからです、と言うので、と大納言は、神様お許しを、龍を殺そうなどと、浅はかな考えが間違っておりました「今より後は(龍の)毛の一筋だに動かし奉らじ」と千回も泣き叫んだ。
願いが通じてか、逆風がふき、船は浜に漂着する。大納言は、あぁ、ここは南海の孤島なのだ、としょげかえるが、実は明石の浜であった。出立が難波で帰還が明石。阪神電車から山陽電鉄に乗り継げば一時間で行ける距離。急に話のスケールが小さくなるように思えるが、この時代では日常的感覚で実感できる世界の境界とはこのあたりだったのでしょう。でも、土地勘が働く地域の広さという意味ならば、現代とあまり変わらないように思える。
大納言は疲れ切って自力歩行も困難な状態。国司(くにのつかさ)、今で言うなら明石市長が見舞いに訪れるが、その哀れな姿を見て思わず失笑。手輿(たごし)に乗せられて、何とか屋敷へ帰還。そこへ雲隠れしていた配下の者たちがのこのこと現れ、いやぁ、「龍の頸の玉」が手に入れなかったので、何とも面目なく、お屋敷にもお伺い出来ずにいました、平にご容赦、と言い訳するのに対し、いや、それで良かったんだ、龍は雷の仲間、お前たちが龍を捕まえようとしたら、この私も殺されていただろう、と咎め立てしない。その代わり、怒りはかぐや姫に向かい「かぐや姫てふ大盗人の奴が、人を殺さむとすなりけり。家のあたりだに、今は通らじ。男どももな歩きそ」。可愛さ余って憎さ百倍。逆恨みも、こういう男に良くあるパターン。加虐的ストーカーにならなかっただけでも可とすべきか。これを聞き及んだ元の正室は、それ見たことかと大笑いしたとか。
★★ エントリー・ナンバー_5 中納言石上麻呂(ちゅうなごんいそのかみのまろ) ★★
最後に登場する中納言石上麻呂の逸話は地味に惨めである。
彼が要求されるのは「燕の子安貝」(つばめのこやすがい)。姫がなぜこれを欲したのかは良く分からない。読んで字のごとく「子安貝」なのだから安産のお守りのようにも思えるが、姫はまだ未婚であるし、彼女の要求物が急に現実的・実効的なものに変化したとは思えない。殷王朝で遣われた貨幣だとも言われるが、骨董収集愛好家であったとも思えない。第一、調べたことがないので何とも言えないが、我が国において殷王朝の存在が一般的に認知されたのはもっと後代のことだろう。「仏の御石の鉢」からの並びから見て、何か特別な魔力を持ったものと想定されていたのだろうと想像する。
「燕の子安貝」を手に入れるのに、中納言は大海に出立する必要はなかった。燕はどこにでも飛んでいる。「大炊寮」(おおいりょう)というから、宮中の仏事・神事・宴会などの食事を用意する厨房の屋根に、燕が多くの巣をかけているという。ならばことは簡単だ。だが、どんな風にして手に入れる? 燕を捕まえてみても子安貝は見つからない、どうやら産卵するときに子安貝を産み落とすらしい。ある家来が言う、巣のある穴の前に足場を組んで見張らせることにしてはどうかと。おぉ、それだ! と、中納言は喜んで即実行。組んだ櫓は二十基。当然のことながら、その騒がしさに燕は用心して巣へ戻ってこない。
そこへ物知り老人が現れる。あれじゃ上手くいきませんよ、作戦を立てましょう。足場はみな取っ払って人気をなくすこと。こっそり隠れて見張るんですよ。運動神経に秀でたアスリートを選んで籠に乗せ、ここぞ、というとき、そっと籠を引き上げて取らせるのです。おぉ、それだ! 今度も中納言は喜んでその通りにさせる。だが燕に産卵の気配が見えるので、家来を籠に乗せるが上手く取れない。中納言は苛ついて、だったら私が、と自ら籠に乗り引き上げされる。
それらしき「平めるもの」に触ったので、よし、急いで籠を下ろせ、と命じる。従者が慌て綱を強く引きすぎたので、綱がプツンときれて落下。腰部を骨折して失神。それでも目覚めると、子安貝を手に入れた嬉しさから、早く灯りを持ってこいと命じる。ところが、握りしめていたものは、子安貝ではなく燕の糞だった、という二重の落ちがつく。
この怪我と作戦の失敗から中納言は衰弱する。かぐや姫は哀れに思って歌を送って見舞うが、その返歌をしたため終えたとたんに絶命。自分で考えないで、人の言うとおりにしようとして失敗を繰り返す、というおとぎ話のパターン通りの展開になっている。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
以上、『竹取物語』の求婚者に課せられた試練を五例、具体的に見てみた。当初は、簡単な引用で済ませて論を進めるつもりだったのだが、今は便利な時代、ネット検索すればあちこちでその原文が読めた。半世紀以上前の印象、現代人の私にも読みやすく、かつ、面白い、がそのまま蘇ってきて、思わず長い引用になってしまった。理屈の方が間延びしてしまったが、まぁ、良いでしょう。面白いものは、何度読んでもおもしろい。
それに、求婚者に試練を課するのではなく《謎かけ》で挑む例として、ご存じプッチーニの『トゥーランドット』から、それの元となった『千一日物語』の『カラフ王子と中国の王女の物語』、さらには、アラビア半島からペルシャにかけて広く伝わっている「謎かけ姫物語」まで、かなり資料を集めていたのだが、整理しきれなくなったので今回は引用を断念しました。デル・モナコの歌う『誰も寝てはならぬ』を聴きながら、居眠りをしてしまった次第であります。
本論に戻る
さて、大急ぎで本論に戻ろう。
配偶者を得るための「試練」は、この『竹取物語』と『魔笛』とでは、どう違うのか?
誰が「試練」を与えるのか、という、この「誰が?」に注目して考えていただきたい。
『竹取物語』の場合、試練を与えるのは《かぐや姫本人》あるいは、その父親である《竹取の翁》である。後述するが、これは当然でしょう。
ごく普通の人々、仮に平民と呼ぶとして、この平民の娘が求婚されたとしても、その求婚者に《試練》が課せられるようなことは、まずあり得ない。先に恋愛があって、恋愛があれば自ずから婚姻に至る。
"June Bride" という言葉がある。六月に結婚する花嫁は幸せになれる、という意味で使われていて、結婚式場の販促パンフレットに引用されていたりする。ローマ神話の主神・ユピテルの妻であるユノ(Juneの語源)が結婚・出産を司る女神であったからだ、という風に、その根拠が説明されている。西欧では3~5月が農繁期でこの時期の結婚が禁じられていたからだという、より現実的な解釈もある。だが、これは「はっきりと言いにくい事実を裏側から述べたもの」であるように思える。
実際はどうだったのか? 農繁期であろうがなかろうが、若い男女が恋愛するのに季節は関係ないだろう。春夏秋冬、農繁期・農閑期、の関係なく、恋人たちは愛を囁きあっていたはずだ。だが西欧諸国は我が日本より寒い。本格的な春になって、やっと恋人たちは屋外で自由に愛の交換ができた。だったら「あっ、出来ちゃったみたい!」と認識されるのは6月ごろになる。これが "June Bride" の正体でしょう、間違いなく。
アメリカには、"Shotgun Wedding" という言葉もある。"I'm pregnant."
と娘が告げるのに、"I don't know." と逃げまくる男に責任を取らせるための、これは手っ取り早い方法であった。
この平民の世界では《試練》などという面倒くさい手続きは不要である。
《試練》が大きなテーマとなるのは、王族であったり貴族であったり、つまり《やんごとなき》階層の人々の場合である。理由は明白。やんごとなき人々は、領地・領民・財産などを領有しているからである。婚姻によってその領有物が四散してしまってはならない。逆に婚姻を、領地・領民・財産などの領有を強化・拡大のツールとして利用しようとする。だから《試練》による求婚者の選別という手続きが踏まれわけである。また《試練》を受けるための条件も、例えば「他の王子である」という風に限定されてくる。母系から父系へと領有権が移行した後の時代になると、娘とその父親がタッグを組んで《試練》の出題者となるのは当然の成り行きだろう。
『共同幻想論』が一般化させた言葉で述べるならば、求婚者に課せられる《試練》とは、次のように定義できるだろう。
領有権の保持・拡大が重要視される《やんごとなき》階層社会においては、
〈恋愛 → 婚姻〉という《対幻想》領域は、
〈一族・部族・国家〉という《共同幻想》に半ば浸食された状態にある。
《対幻想》領域が《共同幻想》に半ば浸食されているという対立関係を、
《止揚》してゆくための力学的モーメントが、求婚者に課せられる《試練》なのである。
ここで重要なのは、
娘や姫の「この男と結婚したい、あるいはこの男とは結婚したくない」という《対幻想》的願望は、
「一族・部族・国家の利害」という《共同幻想》的抑圧に半ば浸食されてはいても、
決して屈服させられてはいない、
という事実である。
それは、微妙なバランス関係のうえで成り立っているが、親・一族がいくら望んでも、当の娘や姫が「いやだ!」と言えば、婚姻が強制されることはなかったはずである。最終決定は《試練》の成就に委ねられていたのだから。
さて『魔笛』の場合を見てみよう。
タミーノが心から愛して結婚したいと望んでいるのはパミーナである。はっきりと固有名詞で明示されていないのだが、パミーナは「夜の女王」の娘、つまり間違いなくお姫様。タミーノも出自は不明ながら日本の狩衣を着た他国の王子様。双方とも、婚姻のための《資格》は充分に満たしているわけだ。
ならば、パミーナに求婚するにあたって、誰がタミーノに《試練》を課するべきなのか?
パミーナ自身から、あるいは(父親が亡くなっているのだから、その代理として)母親の「夜の女王」から課せられるのが定石であろう。
しかるに、タミーノに《試練》を与えるのは、ザラストロの教団なのである!
おとぎ話の定石から完全に逸脱しているではないか!
これは、いったい、どういうことか?
アッティラ・チャンパイの論文の標題を思い出していただきたい。それは、
『《魔笛》の秘密、あるいは啓蒙主義の帰結』
また、今回の始めに私が書いた、近代・啓蒙主義の一属性を思い出していただきたい。それは、
近代・啓蒙主義とは「社会がこうあるべきと示した規範を遵守して、ノーマルな人間であることを強要する」時代です。
再び『共同幻想論』が一般化させた概念で述べるなら、
タミーノが、パミーナや夜の女王から課せられた試練に挑むのではなく、
ザラストロ教団の課した試練超克に向かうのは、
《対幻想》が完全に《共同幻想》に屈服させられたことを意味している。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
1891年の『魔笛』初演の時点で、これからやってくる近代・啓蒙主義の時代には、結婚の形態はすっかり様変わりしてしまうことを、モーツァルトは敏感に感じ取っていたのだと思われる。
また、それが、どこに行き着くかも。
今までなら、結婚に至るためには、求婚相手から課せられる《試練》を克服する必要があった。たとえどんなに無茶なものであっても、その《試練》を克服して、相手とその親に、その家(=内)の男として認められる必要があった。青年たちは、嬉々としてその《試練》に立ち向かったのであった。
だが、今後次第に成熟してゆくであろう近代・啓蒙主義社会では、どうやら様相が違うようだ。相手とその家族に認められるより前に、「社会がこうあるべきと示した規範を遵守して、ノーマルな人間であること」を証明しなければならなくなる。いや、今までにはなかった、より大きな規模の権威によって、つまり国家的権威でもって、それを証明して貰わねばならなくなるのではないか。
つまり、《証文》を発行するのは《国家》なのだ。
あるいは、国家権力によって権威づけられた公的組織なのだ。
ザラストロの教団は、この「証文を発行するの国家、あるいは国家権力によって権威づけられた公的組織」の最初の形態として、聴衆の前に提示されている。
そして現在、この数十年の間に、民主主義国家は、なかんず我々の住まう日本国は、220年前にモーツァルトが予見したように、『啓蒙主義の帰結』の最終ステージにはまり込んでしまったように思える。
天才のおぼろげな予感が的中してしまったのだ。
ページの上段へ
--【その9】了--
残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ