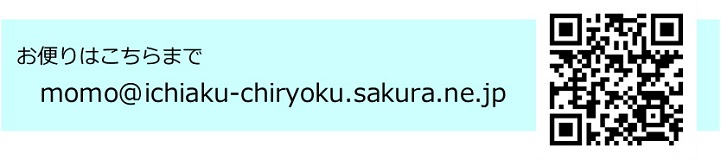映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。
何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?
今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。
ウィーンに出るなら、新しい看板曲が要るぞ!
残された時間は短い。
じっくりとモーツァルトを聴こう。その20
2023/11/02
『猫踏んじゃった』の不思議
今は昔、小学校の3年生か4年生だった頃、音楽室での授業が終わった時の光景を想いだしていただきたい。もし優しい先生だったとしたら、何人かの女子児童がピアノのまわりに駆けよって、かわるがわる鍵盤に触れ、ポロン、ポロン、と小さな音を鳴らしていただろう。あの頃のピアノは、今以上にピカピカに光っていた。恐るおそる鍵盤を叩いてみて、きちんと音の出る適度な強さがのみ込める頃には、隣の子の肩に押されてわきに押しやられてしまう。一人が独占できる時間は数十秒だったが、なかには得意げに曲を弾き出す児童もいた。それは決まって『ネコ踏んじゃった』でした。
あれは不思議な曲です。見よう見まねで誰にでも弾ける。でも、おそらく誰一人としてその譜面を見たことはない。逆に、先に譜面を見せられたとしたら、たいていの子どもは即座に弾くのを断念しただろう。だって、楽譜の最初に
"♭" が六つもついてますから。私なんぞは、「ハニホヘ」「ヘトイロ」「ロハニホ」 …… 、と上行4度を6回数えて、やっと〈変ト長調〉に至りつく。
興味のある人は、譜面をご覧になってください。
この、譜面を見ると極めて難しそうなのに、譜面なしだと超簡単、という不思議な現象がなぜ起こるのか? じつは、今日の話の枕にその〈分析〉をしてみたのです。これがけっこう面白くて、ドンドン分量が増え、今日の本題から外れてしまう勢い。で、いったんわきに置いて先に進みます。
【トルコ行進曲』&『エリーゼのために』、共同主観的〈音楽記号〉として
5年生・6年生になると、授業の後、音楽室のピアノで弾かれる曲が変わる。
モーツァルト ;『トルコ行進曲』
ベートーヴェン ;『エリーゼのために』
一気に大作曲家の作品が登場する。さすがにこの2曲となると、『猫踏んじゃった』みたいなわけにはいかない。譜面を前にして指使いまで指導してもらわないと、きちんと弾けるようにはならない。他の子どもたちより少しお洒落な洋服を着せられていた、あの女の子たちは、きっとピアノの弾ける大人に習っていたに違いない。まだ街ではピアノ教室の看板をあまり見かけることがなかった、そんな時代でした。
この2曲はともに変化記号の付かない「イ短調」で始まる。だから、全曲は無理としても初めのテーマ部分は、初心者用副教材としてうってつけだったのだ、と想像する。ドレドレ、ドソミソ、ドレドレ、ドラファラ、なんて〈おさらい〉ばかりさせられている、その渦中で、この2曲に出会う。もう大喜びで練習したはずだ。
楽譜に興味のある人は → 『トルコ行進曲』 『エリーゼのために』
それにしても、ピアノの音を背後に教室を出て行った私が、彼女たちが弾いていたのは『トルコ行進曲』とか『エリーゼのために』の断片であった、と認識しているのは何故なのだろう? これが不思議なのだ。
年代で言えば、 1958年か 1959年。我が家の場合なら、夕食後の楽しみはもっぱらラジオで、鴨居の上の5球スーパーから流れてくるのは、ほとんどが流行歌か寄席中継であった。『からたち日記』とか『おーい中村君』などの歌詞は、いまでもスラスラと出てくる。同じように『目黒のさんま』なんかも覚えてしまっていて、お客さんの前でさわりを語れば、賢い坊っちゃんだ、などと褒められて、絵本を買ってもらえたりした。
しかし、西洋古典音楽にふれる機会はほとんど無かった。でも〈皆無〉ではなかったのだろう。
想像するに、まれにラジオから流れてくるのを聴いて、A君も、B君も、C君も、みな一様に、西洋古典音楽の〈おぼろげな断片〉を獲得していたのだと思う。それが何かの拍子に会話の中に出現する。自分には出来ないことをする異性に興味を持ち始めるころだ、噂話に放課後のピアノ演奏が出てくる、 ― このあいだD子さんがピアノを引いていただろう ― あぁ、あの曲 ― 『トルコ行進曲』だな ― いや、それはE子さんで、D子さんは『エリーゼのために』だ ― 、という風に。
語り合うことで〈おぼろげな断片〉が確かな認識となる。ただし〈指示表出〉の具体性が極めて希薄であるから、共同主観的〈音楽記号〉として定着する。
ヴェニスといえばゴンドラ、ニューヨークといえば摩天楼、といった具合に〈地理的記号〉がいつの間にか身についていたのと同じように。あるいは、相対性理論といえばアインシュタイン、ノーベル賞といえば湯川秀樹博士、とかいうような〈歴史的偉人記号〉のように。
『トルコ行進曲』忌避の心理
中学校に入ると、音楽の授業には「鑑賞」とか「音楽史」とかいった時間が加わる。この授業が共同主観的〈音楽記号〉の定着を、さらに強固なものにする。
このシリーズの『その12』でも同じことを書いたのだが、教科書の裏表紙見返しには〈超簡略 西洋古典音楽史 一覧〉があり、作曲家の顔写真とその代表作が列挙されていた。そこには、演奏時間で5分程度のこの2曲が、作曲家の代表的大作群に伍して堂々と列挙されていた。こんな具合に。
モーツァルト :トルコ行進曲、アイネ・クライネ・ナハトムジーク(小夜曲)、
(交響曲)ジュピター、(歌劇)フィガロの結婚、(歌劇)魔笛、
ベートーヴェン;エリーゼのために、クロイツェル・ソナタ、(歌劇)フィデリオ、
(交響曲)英雄・運命・田園・合唱、(ピアノソナタ)悲愴・月光・熱情
多くの人はここで、西洋古典音楽を「ひとかたまりの言語群」として認識する。それには意味的な実体がない。そのなかで、『トルコ行進曲』と『エリーゼのために』だけは、すでに〈おぼろげな断片〉から共同主観的〈音楽記号〉へと成長させて意味を保持している。だから、この2曲が西洋古典音楽という〈指示表出〉に対する〈自己表出〉として働く。するとどうなるか?
西洋古典音楽という森に分け入る道が見えていても、『トルコ行進曲』『エリーゼのために』という道標だけが見える。そして、これ知ってる、もう知っている、と森に分け入ることを止める。そして、そのまま大人になる。
これは仕方の無いことである。趣味・文芸の分野だけでも分け入るべき多くの森があるし、さらに成人すれば、家庭と社会のなかで果たすべき役割の成就に忙殺させられる。それが我々の人生。
私などは、このしばらく後、あるきっかけで西洋古典音楽に〈目覚めて〉しまうのだが、最初にたたき込まれたこの固定観念からなかなか自由になれなかった。
例えば、「モーツアルト ピアノソナタ全集」というCDを入手したとする。もうすでにいくつもの「全集」を持っているのに、別の演奏家のものがあればまた欲しくなるのだ。たいていは5枚組で、CD1から聴き始める。だが何故か、『イ長調 K.331 トルコ行進曲付き』まで来ると、これを飛ばしてしまうのだ。この忌避の心理は上手く説明できない。イヤになるほど『イ長調 K.331 トルコ行進曲付き』を聴いてきたわけでもないのに。小学生のころ獲得した、共同主観的〈音楽記号〉としての『トルコ行進曲』が、無心に音楽にむかう心情を邪魔するのである。
「聴け、これがトルコ行進曲だ!」というような、演奏を聴かせてくれ。
この『トルコ行進曲』を忌避してしまうという心情は、私だけではなくて、モーツァルトについての詳細な手引き書を書いている専門家にもあるように思える。例えば『モーツァルトのいる部屋』で井上太郎さんはこう書いている。(p.139)
やや素っ気ないメヌエットをはさんで、フィナーレのトルコ行進曲が始まる。この曲は、あまりにもポピュラーになりすぎた。それはモーツァルトにとって不幸なことである。なぜなら、「モーツァルト? ああ、あのトルコ行進曲を作った作曲家か」で片づけられることがあるからだ。この曲でモーツァルトを片づけてしまったら、あまりにもかわいそうである。それにしてもこの曲、なぜか早く弾かれすぎる。速度の指定はアレグレットなのである。
『K.331』の〈メヌエット〉を「やや素っ気ない」と評しているが ― 私も同感である ― 、井上さんの〈トルコ行進曲〉の解説もまた「まことに素っ気ない」ではないか。曲の解析も、曲を聴いた感想も、何一つ述べられていない。
〈この曲でモーツァルトを片づけてしまったら、あまりにもかわいそうである〉という文面は、世間一般のトルコ行進曲の受け取り方にたいする不満の表明であって、トルコ行進曲そのものの論評ではない。さらにこの一文は、トルコ行進曲はモーツァルトの代表作に値する作品ではない、と言っている。これは大胆な意見である! ― 実は、私も同感であるが ― 。
続けて〈それにしてもこの曲、なぜか早く弾かれすぎる。速度の指定はアレグレットなのである。〉とある。一見してこれは演奏者に対する不満の表明のように思えるが、そうではない。実は、どのような曲としてトルコ行進曲を聴けば良いのか、いまだに確信が持てない、という彼自身の戸惑いの表現である。井上さんは、演奏者に八つ当たりするような論評を書く人ではない。仮に演奏者が「アレグレットですね。かしこまりました」と素直に応じたとしても、じゃ、BPM(Beats
Per Minute)をいくらにするかは演奏者次第。奏者が「四分音符=120」で弾きだしたとして、奏者に向かって、「速すぎるじゃないか、そこは、アレグレットだよ」と注文を付けても、「えっ? アレグレットで弾いていますが
…… 」と言い返されるだけのことだ。
ちなみに、〈速度の指定はアレグレット〉とあるが、『その14』でふれたとおり、モーツァルトの原稿にはこの速度指定はない。後の出版のさい、市井の演奏者の便宜のためを思ってか、編集者が勝手に付加したものである。
つまり、歯切れの悪い文章を書いている井上さんの本音は、実は、こういうことなのだ。
もう長らくトルコ行進曲を聴いてきたが、おぉっ、これだ! と思わせるような演奏にであったことがない。「聴け、これがトルコ行進曲だ!」というような、演奏を聴かせてくれ。
はい、分かりました。
では、これから「聴け、これがトルコ行進曲だ!」というような演奏を聴いていただきます。
ファジル・サイ & ユジャ・ワン
次の二人の演奏をお聴きください。下の画像クリックで "You Tube" の動画が開きます。
上が、ファジル・サイ。トルコのピアニストです。本場物です。
下が、ユジャ・ワン(王 羽佳)。名前のとおり、中国は北京出身。


『トルコ行進曲』はどのようにして作曲されたのか?
いかがですか、スカットされたでしょう。心のモヤモヤがいっぺんに吹き飛んでしまう、そのような演奏です。
でも、もしかすると、これは〈トルコ行進曲そのもの〉ではない、と意義を唱える方がおられるかもしれません。これは "transcription"(編曲)じゃないか、トルコ行進曲を素材にした "improvisation"(即興)じゃないか、と。
それには、こう答えましょう。
では、この演奏は〈トルコ行進曲ではない、何か別のもの〉になっていますか? いいえ、〈トルコ行進曲〉そのものです。トルコ行進曲の "esprit"(エスプリ)を、そのまま、素直に表現すればこうなります、と。長らくモーツァルトの音楽を聴いてきて獲得した "モーツァルトらしさの実感" から、つくづくそう思うのです。
モーツァルトが、後に『ピアノソナタ イ長調 トルコ行進曲付き』(K.331)と名付けられるこの曲を創ろうと思いたったとき、モーツァルトの頭の中にあった曲のイメージはいったいどのようなものだったのだろう?
彼はどのような曲を創ろうとしたのだろう?
ちょっと、想像力を目覚めさせて、モーツァルトの心情を推しはかってみようではないか。
ここでも手がかりを与えてくれるのが、アルフレート・アインシュタインの『モーツァルト その人と作品』である。『K.331』に関する記述をそのまま引用しよう。(p.337)
a)これにつづいてあの《人気ソナタ》、イ長調(K.331)がくる。これははじめに変奏曲、終りにトルコ風ロンド、そして中央にメヌエットあるいはむしろテンポ・ディ・メヌエットを持ち、たいへん多くの人々にモーツァルトの最初の概念を与えてきたものである。しかしこの曲は例外的な作品で、むしろミュンヒェンでの『デュルニッツ=ソナタ』ニ長調(K.284)と対をなすものであるが、ただこれははじめに変奏曲をおき(もちろん比較的短かく、名人芸的な点も少ない)、ポロネーズの代りに、舞曲形式のなかでも最もフランス的なものを選び、純正なバレーの場面で閉じている。b)なるほど、或るドイツ主義ぶった教授は変奏曲の主題の《ドイツ的》素姓を指摘しようと努め、最も純ドイツ的な音楽家の一人はこれを新しいオーケストラ変奏曲の基礎として選んでいるが、この主題は実際にはたいへんフランス的で、たいへんいやこのうえなくモーツァルト的である。なかんずくフォルテによる結尾の強化がモーツァルト的であるが、これはのちに、ゲーテの『すみれ』のモーツァルトの作曲(K.476)のなかに象徴的な力をもって帰って来る。c)いたるところに『デュルニッツ=ソナタ』の充実と音響の感覚性が見られるが、ただそれが、イ長調が二長調からの高揚を意味するのと全く同じように、高揚されている。そしてトルコ風ロンド(アルラ・トウルカ)の短調はここでもぶきみな副効果を欠いていない。
(K.311)イ長調は、(K.284)ニ長調と、対をなす
この十行ばかりを読み解くだけで一回分の分量になりそうだ。極力簡潔に進めていこう。
便宜上、a),b),c),の三つの部分に分けて、読んで行く。
a),
冒頭で、『ピアノソナタ イ長調(K.331)』の受容のされかたを端的に述べている。モーツァルトと言えばこの曲、と言うほどポピュラーである、しかし実は「例外的」である、と。この「例外的」は、「ソナタとは言うが、一般的に云うソナタ形式ではない」という意味と「典型的なモーツァルトというより、モーツァルトとしては例外的な」という両方の意味で使われている。
「『デュルニッツ=ソナタ』ニ長調(K.284)と対をなすもの」とはつまり、作曲家は、もう一度『デュルニッツ=ソナタ』のような作品を作ろうとしていた、ということ。(K.331)は(K.284)の続編として書かれている。これはまことに鋭い指摘である。ここに、我々を悩ましてきた〈トルコ行進曲の謎〉をとく鍵が隠されている。
b),
この部分は解り難い。アインシュタインが批判している対象が、我々には不明であるからだ。おそらく、イ長調(K.331)は「例外的」な作品だと見なされていて、音楽学者たちはモーツァルトの作品として積極的に評価することに窮してきた。そこで、第1楽章の変奏曲の主題に、むりやり「《ドイツ的》素姓」を見いだすことで作品の権威付けをしようとする人が現れた、という事象に対する批判だと思われる。「或るドイツ主義ぶった教授」とは誰のことなのか、私には分からない。
それに対してアインシュタインが「この主題は実際にはたいへんフランス的」などと書くから、余計に混乱させられる。この主題は典型的な「シチリアーノ」であると言われている。シチリアーノならばイタリア的じゃないか、と我々は単純に連想してしまう。実は、イ長調(K.331)を含む一連のピアノソナタが、パリで作曲されたのか、ザルツブルクに帰ってからなのか、という議論が、一時期交わされたらしい。このときアインシュタインは「パリで作曲」派だったから、あえて「フランス的」と言ったのだ、ということでここは納得しておこう。
事実、その直後に「たいへんいやこのうえなくモーツァルト的である」と言い換えて、主題の性格を「国」と関連づける議論を停止している。「なかんずくフォルテによる結尾の強化がモーツァルト的」という風に、「旋律線そのものにモーツァルトを聴く」手法にたちもどる。
ちなみに「最も純ドイツ的な音楽家の一人はこれを新しいオーケストラ変奏曲の基礎として選んでいる」というのは、マックス・レーガー『モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ』のことだろう。聴いていただけば分かるように、この曲は、モーツァルトの主題をそのまま転用しているが、極端な〈レガート〉で演奏することで〈シチリアーノ〉のリズムを完全喪失している。一向に歩き出さないブラームス、みたいな音楽である。
c),
ここでやっと第3楽章『トルコ行進曲』が登場するのだが、それがなんと「そしてトルコ風ロンド(アルラ・トウルカ)の短調はここでもぶきみな副効果を欠いていない」のたった一行。おいおい、これだけかよ。アインシュタイン先生も、『トルコ行進曲』忌避の心情に囚われていたわけか。
でも「ぶきみな副効果」なんて言われても、何のことかサッパリ分かりませんわ。「トルコ風ロンド(アルラ・トウルカ)の短調」は、どう聴いても、賑やかなドンチャン騒ぎ風であって、「ぶきみな感じ」は微塵もないように思うのだが。
これは翻訳による語義のズレではなかろうか。もし、原文が "Ueberraschung"(独)→ "Surprising"(英)だったとしたら、 "Surprising" には「おどろおどろしい」という意味も含まれるようだから、それを「ぶきみな」と訳したのかもしれない。これは「勘ぐり」のまた「勘ぐり」である。私が理解できるドイツは「おはようございます」のレベル、英語だって「郵便局はどこですか?」ぐらいのもの。だからこの勘ぐりは間違っているだろう、たぶん。
とにかく『K.284』のニ長調に対して、その発展形態である『K.331』は、上行五度のイ長調が選ばれている、という指摘に納得して、我々も音楽そのものに向かって行こう。
ピアノ独奏は、〈変奏曲〉を重要視すべし。
モーツァルトは作曲家であるより以前に卓越したクラヴィーア奏者であった。それにしては「ピアノソナタ」として残されている作品が意外に少ない。さらに、クラヴィーアの教師として弟子や貴族の婦女子に多くの教材を提供していたはずだ、と考えると、「ピアノソナタ」の少なさがますます不思議に思えてくる。
その理由はいくつか想像できる。まず、当時のクラヴィーア演奏は即興が多かった、ということ。その場合は楽譜が残らない。あるいは教材として示した断片は出版に至らなかった、という事情。
対照的に、ピアノ協奏曲の作品数はかなり多い。管弦楽との合奏だから必ず楽譜が必要だったわけだ。しかし『第26番 ニ長調』(K.537)のように、ピアノ譜の一部が右手の旋律線だけのものもある。ここからも、必要がなければ楽譜なしで済ませた、という事情がうかがえる。後世の人が振った通し番号で比較してみると、我々が作品数として認識しているのは、ピアノソナタの 18 曲、に対して、ピアノ協奏曲は 27 曲である。
残されたピアノソナタが少ないもう一つの理由として、ピアノ独奏曲としては、ソナタ以上に〈変奏曲〉が演奏されていた、という事情があったからではなかろうか。ロマン派以降になると、ピアノ作品はいったん楽譜に定着させられて、その後(作曲者とは別の演奏者によって)演奏される、というパターンが増えてくる。しかしモーツァルトの時代は、作曲者がすなわちクラヴィーアの演奏者であった。その場合は、即興演奏に適した〈変奏曲〉が好まれたのではなかろうか。
現在では、モーツァルトのピアノ独奏作品としてはソナタばかりが演奏されるようである。CDも「ピアノソナタ(全)集」は数多くリーリースされているが、「変奏曲(全)集」というものには出会ったためしがない。幸い手元に、イングリート・ヘブラーの弾く "COMLETE WORKS FOR PIANO"(ピアノ作品全集)という10枚セットがある。それに収録されている変奏曲の曲数を数えてみると、13曲もあった。これらの変奏曲、聴いてみると、みなチャーミングな曲ばかりだ。上に述べたように、これ以外にも、楽譜として残されなかった演奏が数多くあるはずはずだ。
ここで確認すべきは、「モーツァルトは、ピアノ独奏曲に向かう時、ソナタ以上に変奏曲への情熱を持っていた」ということ。ソナタ形式ではないから「例外的」では決してないのだ。大げさな言い方になるが、「ソナタ形式をもって、音楽の最高形態とする」という「19世紀ドイツロマン派中心主義」の音楽史観から自由になっていないと、モーツァルトを聴き損なうことになる。
【】
さて、『ピアノソナタ ニ長調(K.284) デュルニッツ』である。この曲は 1974年 ミュンヘンにおいてデュルニッツ男爵の求めに応じて書かれた、と云われている。モーツァルト自身、この曲をとても気に入っていたようだ。事実この曲は、 1977年 のマンハイムからパリ遠征時の、彼の主要レパートリーであった。その途中アウクスブルクでシュタイン製のピアノに出会った時も、この曲を弾いている。
その当時の彼のピアノソナタは、 15分 程度のものがほとんどであるが、この曲は 30分 ちかい長さを持っている。最終楽章の変奏曲だけで、 15分 という分量がある。長さだけではない、それまでのクラヴィーア独奏曲の水準から、一気に二段階ほどバージョン・アップさせたほどの表現力を獲得している。
とにかく聴いてみてください。今は指揮者として活躍している、クリストフ・エッシェンバッハ(Christoph Eschenbach)、30歳の時の演奏です。楽譜付きです。 第3楽章は(9:00 〜 )
1783年 音楽家としての自立を目指したモーツァルトは、ウィーンでのプロモーションのために新曲を創ろうとした。そのとき真っ先にイメージしたのが、この『デュルニッツ・ソナタ』であった。よし、あのような曲をもう一つ、と考えた。『デュルニッツ・ソナタ』の中核は最終楽章の変奏曲であったから、今回は、その変奏曲から作曲を始めたはずである。それが、そのまま第1楽章となる。その時、主題に選んだのが、シチリアーノ風の旋律であったことに、彼の作曲家としての自負心が見えないだろうか。
シチリアーノ(シチリアーナ、とも)は、 6/8 拍子 もしくは 12/8 拍子。つまり〈旋律線が長い〉のである。付点が付いているのは舞曲ゆえんのことだろうが、テンポはゆっくりしていて、舞踏的というより〈何かを口ずさみながらの、そぞろ歩き〉という雰囲気が濃厚である。
シチリアーノといえば、すぐに思い浮かぶ曲がいくつかある。バッハ『フルート・ソナタ』(BWV1031)(*偽作とも)、フォーレ『ペレアスとメリザンド』、それにモーツァルト自身の『ピアノ協奏曲23番』(K.488)、等に含まれるシチリアーノである。これも聴いておこう。シチリアーノのイメージをつかんでいただきたい。
バッハ『フルート・ソナタ』(BWV1031) 第2楽章
フォーレ『ペレアスとメリザンド』 シシリエンヌ(Sicilienne)
モーツァルト『ピアノ協奏曲23番』(K.488) 第二2楽章
聴いていただいてお分かりのように、シチリアーノとは、極めて〈情緒性〉〈歌謡性〉豊かなものなのだ。ということは、これ、変奏曲の主題には不向き、ということにならないか? そうでしょう、変奏とはふつう、特徴のある和音進行、特徴のある低音部(バス)の旋律、特徴のあるリズム、などをテーマにして書かれている。〈情緒性〉〈歌謡性〉豊かな長い旋律線は変えようがないではないか。
以前『その15』で、『ピアノソナタ ハ短調』(K.457)が、バッハ『音楽の捧げ物』に触発された部分があるかもしれない、という話をしたが、モーツァルトはここでも大先輩を見習ったのかもしれない。「つまり変奏曲を書くのに、およそ変奏曲には不向きな主題をあえて選んでみせる」という心意気を。
実際、『K.331』の第1楽章は、いつになく慎重に書かれているように思える。
これもまた、エッシェンバッハの演奏でお聴きください。
モーツァルトの心の動きと同調させてみよう。
いかがでしょうか。このように楽譜を見ながらこの変奏曲を聴くと、これがきわめて精巧に創られていることが良く分かる。単純な比較は難しいのだが、『(K.284) デュルニッツ』の変奏曲と比べると、〈不要な音符をとことんまで刈り込んだ、シンプルな緻密さに〉向かっているように感じる。曲は、過度の華やかさに向かうことなく、諧謔性を垣間見せることもなく、落ち着いた進行を続けて、静かな雰囲気のまま、意外にあっさりと終わる。変奏の数も多くはない。前作の 12 に対して、今回はその半分の 6 である。アインシュタインが「もちろん比較的短かく、名人芸的な点も少ない」と書いているのは、このような印象のことを言っているのだろう。
だが意外なことに、実際の演奏時間は前作からさほど短くなってはいないのだ。「名人芸的な点も少ない」とは云っても、冗長さが一切感じられない。過不足のない長さでピタリと曲を終える。モーツァルトは、ここでも一つの進歩を獲得している。
だが、第1楽章変奏曲の筆を置いたとき、作曲家は気付いたのではなかろうか、
こりゃぁ、ちょっと、真面目にやり過ぎたんじゃないかなぁ ―― 、それなりの鑑賞力をもった人ならきちんと聴いてくれるだろうが、そうでない人々は退屈するだろう。耳目を驚かすような仕掛けが何もないぞ、と。
じっさいこの私も「そうでない人々」に属しているから、聴き始めの頃の印象は、あまり面白くないな、モーツァルト的でない、というものであった。
そこで、作曲家は気分転換をはかる。次のメヌエットが「やや素っ気ないメヌエット」(前出、井上太郎)になっているのは、変奏曲でいつになく曲にのめり込み、真剣になりすぎたことに対する「照れ隠し」のように思える。
気のないそぶりのメヌエットが終わる。しかし依然として、第1楽章変奏曲の生真面目さの雰囲気は消えない。「そうでない人々」の気分が沈んだままなのが、手に取るように分かる。では、どうするか?
しばしの思考のすえ、作曲家の頭に閃いたものがあった。そうだ、あれで行こう。あの底抜けの馬鹿騒ぎで終わらせよう。そうすれば「そうでない人々」を大喜びさせることが出来るぞ。そうだ、そうしよう。
かくして作曲家は、第3楽章の冒頭に書く。
"Alla Turca" (トルコ風に、トルコ軍楽隊風に) と。
このような、モーツァルトの心の動きと、彼の目論みに従うならば、第3楽章は「ぶっ飛んで」演奏されなければならない。そう、先ほど聴いていただいた、ファジル・サイ、とか、ユジャ・ワンが演っているように。
いま私が述べたことを、「それって、あなたの妄想でしょ」などと云って、退けないでいただきたい。200年以上前の作曲家の心情をそのまま再現出来ないのは、旧来の音楽史家の正統的な解説だって同じことだ。大事なのは「なるほどそんな風に考えれば、21世紀の我々が、『トルコ行進曲』を、心から愉しんで聴ける」スタイルを創造することである。聴くことだって、創作への参加なのだ。
次回は、(おそらく)私が想像したのとほぼ同じように考えて演奏をしている(と、思える)ピアニストを紹介します。異端の新人ではありません、ドイツの正統的な大家です。
ページの上段へ
−−【その20】了−−
残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ