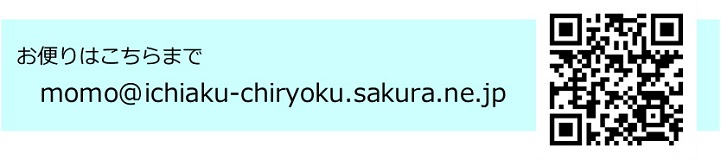映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。
何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?
今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。
残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。 |
|
| 西洋古典音楽といえば、誰もが真っ先に思い浮かべるのはモーツァルトであろう。その音楽は他に比類がないほど耳に心地良い。だが多くの人々は、彼の音楽は《それ以上のもの》であることに気づいている。「死とはモーツァルトを聴けなくなることだ」という言葉が語り継がれるのはそのためだ。この箴言は死を定義するものではない。モーツァルトの音楽の本質を言い当てようとしたものだ。だが果たせず《死》を持ち出したところで中断し、それは《謎》のまま放り出された。幾多の碩学がこの謎に挑んできたが、雲の切れ目にその頂を垣間見たただけで断念している。つまり、誰にでもその《謎》に踏み込む権利は残されているのだ。 |
|
 |
残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。 その1 (2021/11/22) 残された時間は短い …… 、などと書き出すと、あぁ、この人も年齢相応に爾後の経過が楽観できない疾病に取り憑かれてしまったのか、と思われそうだ。だが、そうではない。私は“表面上”きわめて平穏無事に暮らしている。確かに、齢を重ねるごとに体力・気力は低下し、食事の後に飲む薬の量は増すばかりだが、それは血圧やら採血やらの検査値を正常値の範囲に収めるための薬剤である。 それでも、私に残された時間はそう永くは無い。最近とみにそう思い知らされる。 ( …… 続きを読んでみる ) |
 |
死とは、モーツァルトが聴けなくなることだ。 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その2 (2021/12/07) モーツァルトの音楽に魅入られた人なら、おそらく何回も、次の箴言に接した記憶があるだろう。 死とは、モーツァルトが聴けなくなることだ。 この言葉は、死の恐ろしいまでのリアリティとともに、私に迫ってくる。 それが何故なのか、この一句がなぜこれほどまでに“死のリアリティと結びつく”のか、今の私にはその理由をうまく説明することができない。 ( ……本文をを読んでみる ) |
 |
『魔笛』に聴くモーツァルトの本質 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その3 (2022/01/01) 『魔笛』が初演された頃の欧州では、様々な絡繰り(からくり)・仕掛けを弄して聴衆を楽しませる「機械芝居」が大人気であった。『魔笛』でも、三人の童子は気球に乗って降りてくるし、夜の女王は雷鳴とともに出現する。岩山が割れ、水と火の試練があり、動物たちが舞台を駆け回るなど、趣向が盛りだくさんである。つまり、一昔前の見世物小屋と現代のUSJを混合させたような演劇空間を大衆は求めていたのだ。具体例に引き寄せてみるなら、たとえば《引田天功と氷川きよしのコラボ・ショー》なるものを想定すれば、その観客層は《魔笛》のそれと一致するはずである。これが、いま風に言えば《歌芝居魔笛のコンセプト》だったのである。 ( ……本文をを読んでみる ) |
 |
パパゲーノとは、いったい何者。 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その4 (2022/01/22) それにしても、パパゲーノとは、いったい何者。 全身に鳥の毛を生やしているが、それは衣装ではなく、本当に鳥の毛を生やしているようにも思える。 大きな鳥籠を背負っているが、それは何のため? 第一幕の開始早々、『おいらは鳥刺し』と歌うが、「鳥刺し」ってどんな職業? 今日は、この《パパゲーノの謎》を解いてみよう。 ( …… 続きを読んでみる) |
 |
『魔笛』における「アジール(聖域)」の存続 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その5 (2022/02/20) 夜の女王が支配する〈国〉には「アジール(聖域)」が存続していた。そう判断したのは、パパゲーノが「鳥刺しを生業として生きてこられたから」である。しかしこれだけが根拠ではない。私の正直な実感を述べると、『魔笛』は、第二幕より第一幕のほうがより楽しく聴くことができる。それは、夜の女王が支配する〈国〉が舞台となる第一幕では、登場人物の〈欲望〉がストレートに表現され、それがそのまま肯定されているから、ではなかろうか。ところが第二幕になると、一転して〈禁欲〉を維持することが劇を進行させて行く。そこで、欲望・しくじり・お咎め、という三つの視点から、第一幕と第二幕を比較検討してみる。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
啓蒙主義がもたらす《男社会》への予感 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その6 (2022/03/27) 18世紀後半の西欧社会とは、市民社会の形成とともに、旧体制(アンシャン・レジーム)の根幹が揺るぎ、思想的指針としての啓蒙主義が徐々にしかし確実に浸透し、ついにフランス革命に至った、そういう時期であった。では啓蒙主義は、どのような社会を将来の理想として描いていたのだろう。この問いには簡単に答えることができない。幾筋もの流れが拮抗し錯綜している。シカネーダーとモーツァルトも、そのような社会的動向を概念化するような作業は行っていない。彼らは劇作家であり音楽家であって、社会的思想家ではなかったのだから。しかし卓越した創作者であった彼らには、何かしらの《直感》が働いていたに相違ない。今までになかった《男社会》が来るのではないか、という直感が。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
“パミーナ”と“レオノーレ” その《決断》の差 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その7 (2022/05/26) 囚われの身になっている配偶者(あるいは配偶者となるべき人)の救出に向かうという、基本的プロットは『魔笛』と『フィデリオ』に共通している。『魔笛』の場合、囚われているのは女であってそれを男が救出に向かうという、順当な設定になっている。しかし『フィデリオ』の場合はそれが逆。囚われている男を、何と、女が救出に向かう! のだ。しかも《男装》して。ヒロインの二人は、決意して行動に向かうことは共通している。だがパミーナは「一人前の男になろうと試練にむかうタミーノに、同行することを決意する」だけ。レオノーレは「政治犯として収監されている夫を救出することを、自分で決め、自分で戦術を立て、自分で実行する」のだ。この《差》は何に由来するのか? ( …… 本文を読んでみる) |
 |
“おとぎ話”としての『魔笛』 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その8 (2022/06/28) おとぎ話・昔ばなしは、ユング心理学や文化人類学を引き合いに出すまでもなく「全人類に普遍的で、特に無意識のうちに行われている思考原理・行動原理の典型・類型をその基礎に含む」。この“おとぎ話”という観点から『魔笛』の登場人物の心理と行動原理を読み解いてみよう。登場人物は、どこまで普遍的・一般的なおとぎ話・昔ばなしと同じで、どの地点からそれからずれて行くのか? 今回は次の3つのおとぎ話の〔型(パターン)〕で検討してみる。 〔1〕:「幽閉されたお姫様」・「眠り続けるお姫様」を救出するのは「他国の王子様」 〔2〕;「絵姿」に一目惚れ 〔3〕:「魔法のツール」の持つ効力 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
“おとぎ話” の変容 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その9 (2022/08/28) タミーノが心から愛して結婚したいと望んでいるのはパミーナ。はっきりと固有名詞で明示されていないのだが、パミーナは「夜の女王」の娘、つまり間違いなくお姫様。タミーノも出自は不明ながら日本の狩衣を着た他国の王子様。双方とも、婚姻のための《資格》は充分に満たしているわけだ。ならば、パミーナに求婚するにあたって、誰がタミーノに《試練》を課するべきなのか? パミーナ自身から、あるいは(父親が亡くなっているのだから、その代理として)母親の「夜の女王」から課せられるのが定石であろう。しかるに、タミーノに《試練》を与えるのは、ザラストロの教団なのである! このおとぎ話の定石からの逸脱は、何を意味するのか? ( …… 本文を読んでみる) |
 |
主人公の「影」としての他者 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その10 (2022/09/30) タミーノが主人公であるなら、パパゲーノは間違いなくその影である。二人の関係は極めて密接である。パパゲーノはタミーノのまだ見ぬ婚約者の救出に同行し、狂言回しとしての役割を演じながら、タミーノがパミーナを獲得するのと同様に、パパゲーノもパパゲーナを獲得する。しかし「おとぎ話というもの」という視点から見るなら、二人の関係はかなり異質に見える。二人の心理的指向性は、全編においてまったく交わるところがないのだ。なぜ、モーツアルトの二人の化身とも言うべきパパゲーノとタミーノの精神は、分断されたまま放置されているのだろう? これこそ『魔笛』最大の謎である。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
行き場を失うパパゲーノ 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その11 (2022/10/10) ダ・ポンテという人物に関して、我々はまとまった資料を持っていない。数多く書かれているモーツァルトの評伝のなかで、少しばかり言及されている部分で推しはかるしかないのだ。ヨーゼフ二世の死後、多くの資料で、ダ・ポンテはレオポルド二世の不興を買って国外退去命令を受けていた、と書かれている。また、べつの資料には、ダ・ポンテの方がレオポルド二世に愛想をつかして、宮廷詩人としての辞表を出したのだ、と書かれている。我々が知りうるのはこの程度のことだ。だが、このような断片的な情報でも、ダ・ポンテとモーツァルトという繋がりに注目してみると、そこから多くのキャラクターが芋ずる式に引きだされてくる。結論を先走りして言うなら、みなパパゲーノという人格に繋がる人たちである。それも「行き場を失った」パパゲーノに。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
記号としてのモーツァルト 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その12 (2022/12/22) 映画『アマデウス』の冒頭、自殺を図ったサリエリを神父が訪問する。神父は懺悔を促すが、サリエリは応じない。サリエリは自分のオペラの一節を弾き、この曲を知っているかと尋ねる。だが神父は言い当てることが出来ない。サリエリは別の曲を弾くがやはりだめ。ところがサリエリが『小夜曲』を弾き出すなり、神父から当惑の表情が消え、嬉しそうにハミングを始める。サリエリは演奏を止めてしまうが、神父は調子にのって第一テーマを歌いきる。神父はモーツアルトを良く理解していた、と言うことか? 否、「記号としてのモーツアルト」が神父の記憶にたたき込まれていた、と言うだけのことである。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
《トルコ行進曲》が好きになるための努力 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その13 (2023/02/05) 1781年、ウィーンに着いたモーツァルトがウェーバー家と懇意になるのは、ウェーバー家にあるチェンバロが自由に弾けたからであった。あれだけのクラーヴィーア作品を次々と書き続けたモーツァルトが、じつは普段使いのクラーヴィーアにも不自由していたのである。その後父レオポルドがウィーンの息子宅を訪れた時、そこにワルター製のピアノフォルテがあることを発見する。モーツァルトがそれを入手した経緯は伝わっていない。想像をたくましくして言うならば、そのような高い買い物は父親が反対するに決まっているから、黙って購入していたのではなかろうか。だから、その旨を記した父親あてにの書簡が残されていないのだろう、きっと。今回は彼の使用していたクラヴィーアについて考えてみる。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
改めて、モダンピアノの特性を考える。 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その14 (2023/03/15) 我々はピアノを西洋古典音楽の伝統的な音として聴いているが、実は産業革命以後のハイ・テクノロジーで繰り返しバージョン・アップされた後の音を聴いている。Windowsが次第に重たくなるのと同じように、現在のコンサート・グランド・ピアノの重さは 400キログラムを越え、ピアノ線の張力は20トンに達する。まさに超弩級戦艦。では、モーツァルトのクラヴィーアの重さはどれぐらいだったのだろう。うんと軽いだろう。コンサート・グランドの 1/10 ぐらいだろうか? その音は繊細でふんだんに雑味が混ざっている。スタッカートを効かせた奏法なら、どんなに音符が連鎖していても、そのわずかな間隙に無音の時間がはさまる。この静寂を聴き取ることのできる耳を、我々は獲得できるのだろうか? ( …… 本文を読んでみる) |
 |
現代人は低音がお好き! 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その15 (2023/05/04) アメリカのコネティカット州に『ズッカーマン』という、古典的クラヴィーアの楽器工房がある。そこがシュタイン製フォルテピアノの販促プロモーション動画をアップしている。このピアノが素晴らしい完成度なのだ。音色は極めて滑らかで、高音から低音まで見事に均一化されている。鍵盤の動きもスムース。弱音効果・ダンパー効果などの操作性もよさそうである。なるほど、モーツァルトが驚喜した「シュタイン製フォルテピアノ」とはこんなモノだったのか! と感動させられる。だが、その動画で聴く『トルコ行進曲』は、私の空想のなかでモーツァルトが弾く『トルコ行進曲』とは、最後のギリギリのところで一致しないのである。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
第九交響曲『合唱』に、トルコ音楽の響きを聴く 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その16 (2023/06/10) ベートーヴェンの交響曲第9番『合唱つき』を知らない人はないだろう。『歓喜の頌』のメロディーは中学校の音楽教科書にも載っている。歌ったことがなくとも、年末の某『歌合戦』の裏番組として放送されているのを観たことがあるだろう。検索すると、たくさんの解説に出会うのだが、そのほとんどは歌詞に採用されたシラーの詩の解説に終始している。自由を希求する理想、それに至るための不屈の精神、博愛主義、などの文学的解釈ばかり。これは変だ。『合唱』は、新たな聴衆を創造するために、作曲家があの手この手を尽くして創りあげた作品だ。例えば、庶民に親しまれていたトルコ音楽が取り入れられている、といえば驚く人も多いだろう。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
オスマン帝国 ― 脅威と規範 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その17 (2023/07/10) 私は世界史を熱心に勉強したことがない。それでも、ローマ帝国とは? と問われれば、その起源、有名な皇帝、版図の拡大、周辺国家との関係、分裂、衰退と消滅、などを、かなり詳しくのべることが出来る。史実にどこまで忠実かは別として、逸話や映画などでそれなりのイメージを保持している。しかるにオスマン帝国に関しては、ほとんど何の知識も持っていない。アラビヤン・ナイトとか、ペルシャ絨毯とかと同様、オットマン=背もたれのない椅子、トルコ風呂=スティームバス、などという誤用を除けば、〈異国趣味を喚起する記号〉としてしか意識されることがない。しかしこの事実は、我々が『トルコ行進曲』や『第九交響曲』を聴き損じることと、共通の根を持ってはいないか? ( …… 本文を読んでみる) |
 |
『トルコ風』を科学する。残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その18 (2023/08/01) モーツアルトがいたころ、ウィーンに『ヘッツ劇場』という3階建て3000人収容の大劇場があった。そこで開催されていたのは、弱った動物をなぶり殺しにする残酷ショーである。古代ローマのグラディエーターを闘わせる闘技会や、スペインの闘牛を思い起こされる。現代のモラルからみればまことに許容しがたい蛮行であるが、世界史のなかでは度々、このような、ごく普通の人々が熱狂して「集団的エクスタシー」を得ようとする残虐性が出現する。このショーにおいて、観客の興奮度を高めるための「音響効果」が用いられた。それが「トルコ音楽」だった。これが、ウィーンの市民社会における「トルコ音楽」受容の初期形態なのだ。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
コメディ・バレ『町人貴族』残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その19 (2023/09/20) モーツァルト『トルコ行進曲』の分析をしていて、その当時のウィーン市民におけるトルコ音楽の受容の具合を確かめる必要を感じた。調べてみると、モーツァルトの時代よりずっと以前から、トルコ音楽の受容が始まっていたことが分かる。ならば、他の地域ではどうだったのか? もっと以前はどうだったのか? と探っているうちに、何と、モーツァルト『トルコ行進曲』より100年以上も前に、ある喜劇のなかでトルコ風行進曲が賑やかに鳴り響いていたことを知ったのである。時は1670年、場所はパリ。その演目は『町人貴族』。モリエール作の喜劇と記憶していたのだが、正確には "コメディ・バレ" 。音楽と踊りがてんこ盛り。〈宝塚レビュー〉のような傑作だ。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
いざ、ウィーンへ。新しい看板曲を! 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その20 (2023/11/02) 1774年に創られた『デュルニッツ・ソナタ』はモーツァルトの看板曲であった。パリ遠征時にも彼はこの曲を携えてゆき、コンサートのプログラムに載せている。1783年、音楽家としての自立を目指したモーツァルトは、ウィーンでのプロモーションのために新曲を書こうと思いたつ。この時彼の念にあったのもこの曲であった。よし、あのような曲をもう一つ、というわけだ。さて『デュルニッツ・ソナタ』の中核は最終楽章の〈変奏曲〉である。新曲もその変奏曲から作曲を始めたはずである。主題に選んだのがシチリアーノ風の旋律。でもそれは〈変奏曲〉の主題に適しているとは思えない。だから曲は、作曲家の目論見からすこしずれたものとなる。それがそのまま『K.331 イ長調 』の第1楽章となるのだが …… 、 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
クリスティアン・ツァハリアスというピアニスト 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その21 (2024/01/27) ハイドンとモーツァルトが、新しいピアノ・フォルテの《美質》を生かして作曲に励んだ25年間が終わるか終わらないうちに、ベートーヴェンはピアノ・フォルテに《新機能》を求めた。1819年、彼はその第29番目のソナタを出版社に送りつけるに際し「今後私のソナタは、ピアノ・フォルテではなく、ハンマー・クラヴィーアのための、と標記するように」と指定した。ウィーンの巷では、ローゼンベルガー製フォルテピアノに見るように、打楽器を加えるなどして付加機能を盛り込む多様化が進行中であったが、ベートーヴェンは、ピアノ・フォルテの基本フレーム・ワークのバージョン・アップを求めた。それ以降、ピアノは、ベートーヴェンの要求したとおりの発展をする。だが、その見返りとして、ハイドンとモーツァルトが魅入られた《ピアノ・フォルテの美質》を喪失したのである。 ( …… 本文を読んでみる) |
 |
駈けめぐる十六分音符 残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。その22 (2024/03/10) 『ピアノ協奏曲 変ロ長調 K.450 (15番)』第一楽章の聴きくらべをしてみる。モダンピアノとフォルテピアノの演奏で。この楽章は、先に進むにしたがって、クラヴィーアの十六分音符が縦横無尽に音場を駈けめぐるようになる。フォルテピアノでは、十六分音符の飛翔が出現するたびに、あたかも螺旋階段を昇るように高揚感が昂まってゆく。モダンピアノでも十六分音符はたしかに飛翔している。だが、それは常に端正さを保持した水平飛行であり、次第に高揚してゆく上昇感覚が伴わないのだ。この差は、演奏家の解釈というよりも、楽器そのものの特質から来ているように思える。では、ツァハリアスの場合はどうか、彼はモダンピアノの演奏家なのだが …… 、 ( …… 本文を読んでみる) |
|
|
|
| 日本には、ミュージカル映画を正当に評価しない、という奇妙な伝統がある。映画の批評家たちが音曲の嗜みを持たないこと、口を挟む音楽評論家がクラシックもしくはモダン・ジャズ畑の人であること、がその理由である。『サウンド・オブ・ミュージック』は、人気を得た曲目の多さと、老若男女を問わずそれらが愛聴・愛唱されている、という点において群を抜く名作である。しかしまともに論評されないこと甚だしい。そこで、半世紀以上のクラシック音楽愛好家である私が、誠に僭越ながら、多少の解析を試みる。 |
|
 |
その1 (H.28/05/22) 『サウンド・オブ・ミュージック』の日本公開は1965年。大きな話題となり大ヒットした映画だが、批評家たちの評価はあまり芳しいものではなかったと記憶する。ミュージカルの本質とは無縁の位置からの外面的な批判ばかりだった。他のジャンルの映画だったら許されるのに、ミュージカルとなると奇妙なリアリティを要求されるのは何故だろう。 |
 |
その2 (H.28/06/05) ブロードウェイ初演(1959年)の翌年には、ジョン・コルトレーンの『マイ・フェィヴァリット・シングス』がリリースされ、さらに三人の歌手によって立て続けに『ドレミ』の日本語化が行われている。映画の公開に先立って、その楽曲は、我々日本人に広く親しまれるようになっていたのだ。しかるに、そういった進行中の音楽事情を一顧だにしない映画批評ばかり、私は読まされていた。 |
 |
その3 (H.28/06/18) 『マイ・フェィヴァリット・シングス』の解析を行う。歌詞は日本の『ものづくし』にも似た言葉遊びで、ふんだんに頭韻・脚韻を踏んだもの。旋律は近代的音階成立以前のオクターブ三音階。つまり欧州の伝承童謡のパロディではないか。コルトレーンは『カインド・オブ・ブルー』で試みたモード旋法の「モード」をここに発見したのだ、と思う。だからこそ、あれほどまでのアドリブ拡張が可能だった。 |
 |
その4 (H.28/07/06) 『ドレミの歌』が「シンプルなのにこれほど心を打つ」理由を探る。階名がそのまま言葉遊びになっている。耳で聞くと、今、創られながら歌われている、という即興性にあふれた歌だと感じるのだが、楽譜を見ると、同型の節の繰り返しが極めて厳密な規則性によって組み立てられているのが分かる。これはほとんど、バロック音楽の作風ではないのか。 |
 |
その5(H.28/07/29) 『南太平洋』『王様と私』『サウンド・オブ・ミュージック』と続くロジャース&ハマースタインの創作の流れを読んでみる。さらに、アメリカ製ミュージカル全体の変遷を鳥瞰してみる。すると『サウンド …… 』の根本には、ウィーン風オペレッタへの原点回帰があることが見えてくる。流れの中に踏み石として『巴里のアメリカ人』を置いてみると、さらにはっきりと分かる。それはまた、それまでは埒外に追いやられていた「子供」を発見してゆくプロセスでもあった。 |
|
|
|
| 木下惠介はまぎれもなく日本映画の巨匠であるが、黒澤・小津・溝口・成瀬といった監督たちと比べると、論じられる機会が少ないように思える。彼の美質は、あらゆるイデオロギー的表現から自由であろうとする意志力と、過剰な情緒的表現を排して観客の想像力を信頼したことにある。代表作の『二十四の瞳』と戦時中軍部の検閲下で作られた『陸軍』を例に、それを読み解く。 |
|
 |
その1 (H.28/01/15) 映画『二十四の瞳』は壺井栄の原作を尊重して作られている。台詞も原作中の会話をそのまま引用したものが多い。木下が行った原作からの削除と追加は控えめに実行されているが、その差異を確認すると、彼が極めて自覚的に自分の作品からイデオロギー性を排除しようとしていたか、が分かる。 |
 |
その2 (H.28/01/22) 佐藤忠夫は『二十四の瞳』を「日本映画史上おそらくもっともたくさんの涙を観客の涙腺からしぼり取った作品の一つ」と評している。金比羅さま近くの食堂で先生が川本松江と再会する場面は、その白眉であろう。しかしここで二人は愁嘆場を演じてはいない。微笑んでみせる先生と松江の後ろ姿に観客は号泣する。先生が泣くのは、まさに泣くことしか出来ない状況において、である。 |
 |
その3 (H.28/02/06) 木下惠介は、言葉を失い泣くことしか出来ぬ女たちをそのまま認め、そのまま描こうとする。戦時下の戦意高揚を目的とした『陸軍』でも、この彼の基軸はぶれない。ラスト10分は圧巻である。軍部は激怒したと言うが、70年後の我々は純粋に感動させられる。 |
| |
|
 |
発禁になった唱歌たち (27/12/25) 第二次大戦下の日本には検閲という制度があった。「時局にそぐわない」ものを排除するためである。ところが、ごく当たり前の日常を歌った学校唱歌でさえ発禁となったものがある。理由を確かめれば、まさに噴飯モノなのだ。検閲者が時局に過剰適合しようとした結果である。だが、笑ってはいられない。今も同じことがごく当たり前のことのように進行している。 |