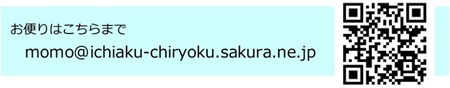一握の知力 > 山之辺古文書庵 > 味覚を問うは国賊 > 八 伏魔殿女名主
八 伏魔殿女名主
ここで音楽担当教諭、U女史が登場する。生徒を虐めることが持てる唯一の技術という教師は多いが、U女史において特筆すべきはその超絶的テクニックであった。
Uは始業のベルが鳴ってから、決まって数分遅れて音楽室にやってきた。すでに授業が始まり静まり返った廊下を、彼女はゆっくりと歩いて来る。靴の踵が、コツ、コツ、と響くのを、音楽室で着席して待っている生徒たちは、頭の後ろに聞いた。これがアンダンテ(歩くぐらいの速さで)なのね、そう言いたげな足音であった。あのなセンセ、もう授業始まっとんや、せめて、アレグロ・マ・ノン・トロッポ(快速に、しかし過ぎないように)ぐらいで歩けや、と私は心の中で呟く。授業に遅れてすみません、という急ぐ気持ちと、大きな足音を立ててはいけない、という慎みの気持ちを表すなら、当然そうなるだろう。授業前からすでに神経戦が始まっている。
音楽室の扉を開けて、彼女はいったん立ち止まる。自分の躾の成果を確認するためだ。菓子折を開けた時のひよこ饅頭の様に、生徒が等間隔に着席しているのを、背後から見るのが好きなのだ。従順な生徒たちは微動だにせず、正面を向いて先生を待っている。この情景が彼女に快感をもたらす。これを見るために彼女はわざと遅れて来る。直ぐに入室しないのは、慌てて着席したばかりの不届き者を探るためだ。体の揺れや息の乱れを悟られた者は、こう言われる。
急に真面目なふりをしたって、お見通しよ。態度で分かるんだから。休み時間にどんな用事があるかもしれないから、あなた方にはちゃんと準備の時間をあげているじゃないの。
自分の遅れを正当化する台詞がそのまま、指摘を受けた生徒の反論を封じ込めてしまうという、超絶技巧がのっけから駆使される。どういう風に喋れば相手へのダメージが大きくなるか、とっくに検討済みなのだ。ピアノの前へ到着するまで彼女は点検の手を弛めない。
そこぅ、教科書はキチンと並べて置きなさい。(慌てて本を揃える音)
背中が曲がってるぅ。パーン(背中を叩く音)。朝ご飯ちゃんと食べてきたの。
森本、名札が出てないよ。
襟が汚れてるぅ。洗い晒しは恥ずかしくないけど、汚れたまんまの服は恥ずかしいよ。
Uが通り過ぎる瞬間、通路側の生徒が緊張のあまり震えているのが分かる。肉体的な暴力を見舞われる訳ではないが、クラス全体が静まり返る中で、駄目だ、何をしているのだ、と言われると、自分の家の躾の「至らなさ」を指摘されたようで堪らない。
やっとピアノの前に到着したUは、白いブラウスに黒のスカート、教科書・楽譜を両手で胸に抱えて、完璧な音大生コスプレ。服装だけは前年の「そこら、テキトーに」の先生と類似だが、頭髪はパーマ、顔は白塗りに金縁メガネ、いずれも手入れの度が過ぎて、こちらこそ洗い晒しで生気が抜けてしまい、チャコール・グレーにオフ・ホワイト、といった塩梅。
彼女は教科書を片手に抱えたまま、ピアノ・カバー(あの黒い暗幕みたいな奴)の一部をまくりあげ、蝶番の付いた演奏者側の上蓋だけを180度返して譜面台を起こす。大切なピアノはキチンと両手で扱え、私の心はまた呟く。
生徒に挨拶もさせず、何の指示も出さず、緊張の姿勢を続けさせたまま、彼女はピアノの無駄弾きを始める。何の工夫もない上向・下向のアルペジオを一頻り続けたあと、今日の授業で取り上げる唱歌の旋律を弾き始める。リズムを大げさに揺らして必要以上の感情を込めようとする。単旋律反復耽溺型の典型だ。清楚な学校唱歌を、ラフマニノフ風に(あくまで「風に」である)弾いてどうすんねや。その格好悪さに生徒たちの雰囲気が少しだれる。するとUはピアノを弾き続けたまま、大声で叫ぶ。
みんな、お聞きぃ。
ト長調の譜面をパット見て、その場でニ長調で弾ける先生など、
そう、ざらに、いないよぅ。
私は音欠けオルガンで教科書に出てくる唱歌を練習し始めて、1年と少し経っている。自分の腕はなかなか上達しないけれど、今弾かれているものが、どの程度の難易度なのかは見当がつく。ト長調の学校唱歌を、テキトーな伴奏を付けてニ長調で弾く位のことは、私でもできる。
先生とは経験をギュッと凝縮させて伝える事を、仕事としている人だ。だから多少わけあり風であっても、宇宙人である可能性が濃厚であっても、私は礼節を尽くして敬ってきた。そうしないと怒られるからではなく、良く思われたいからでもなく、そうするのが自然だと感じていたから。実際にほとんどの先生は、子供に小さな礼儀の心を見つけると、よりいっそう熱意をこめて指導された。礼儀正しいと得をする。
私はこのUに対しても同じ姿勢で接しようとしていた。
中学1年生も終わりの頃、生徒たちは男も女も、2年生になれば本校で怖い怖いU先生に音楽を教わるのだ、厭だ、厭だ、と騒いでいた。私は心底から同級生たちを軽蔑した。嬉しそうに騒ぐな。不安は一人で耐えよ。耐えられなければ転校しろ。音曲の師匠が名人なら、気難しくて怖いか、勝手気ままで何も教えてくれないか、そのどちらかだろう。
私はUが気難しくて怖い先生である可能性の方に賭けて、彼女が期待する躾のレベルに応じようと決めていた。私は音楽が好きなことを自覚し始めていたし、鍛えてもらえるのなら、怖かろうが優しかろうが変わりはない。
しかし一回目の授業だけで、これが大変な思い違いであることを悟った。生徒たちが陰で揶揄していたように『ヒステリー女』という方が、Uの実体に近いことを認めざるを得なかった。私はひどく落胆した。音楽に関して得ることはほとんど無かろう。さらに今後どの様なスタンスで授業に望めば良いのか、全く見当が付かない。
ピアノの無駄弾きはまだ続いている。生徒たちはさんざんいたぶられたあげく、今度は呆れさせられ、一時的な失神状態に陥っている。その瞬間を逃さず、突然今日の唱歌の前奏が始まる。生徒はたちまち正気に返るが、あれー、どうするんだと戸惑う。ピアノが止み、罵声が飛ぶ。
歌いなさいよ。ピアノを聴いていなかったの。前奏は終わってるじゃない。
改めてピアノが前奏から始まる。しかし今まで緊張させられ必死だったから、生徒たちの喉はカラカラ、顎はガクガク。かすれた声、引きつった声、悲鳴の様な声が、バラバラに響く。Uはワン・コーラスでピアノをやめ、先ほど「急に真面目なふりをしたって、お見通しよ」と目星をつけた男子生徒に標的を絞る。
誰だ、変な声出してるのは。
誰だぁ。(と言いつつピアノを離れ、件の男子生徒の側へ行く)
お前か。一人で歌ってごらん。
立つんだよ。立って歌うんだ。
さあ、ターララ、パンパ、パンパ、パン。
これだけ先手・先手と打ちまくられると、相当の悪ガキでも既に自意識は消え去っている。半泣きでかすれ声をあげるしかないのだ。
ほーら、また外した。
ターララ、パンパ、パンパ。パン。
旋律が駄目なら、リズムぐらい合わせてごらんよ。
そーれ、ターララ、パンパ、パンパ。パン。(指揮棒で生徒の背中を叩いて! 拍子をとる)
駄目ねえ。気持ちの準備もしないで、授業の最初からダレてるから歌えないのよ。
みんなぁ。一緒に歌ってるから、自分の声は分からないだろう、なんて思わない事よ。五十人ぐらいの声は、ちゃーあんと聞き分けられるんだから。私ぐらいになればね。
もう生徒たちは、次に自分が標的にならないように、ということだけを念じている。変な声で歌えばやばい、かと言って、もごもご歌うのはさらにやばい。眼は正面の黒板を見つめ、しかも何処にも焦点を合わせない。自分が相手を見ないなら、相手も自分を見付けないはずだ、とでも願うように。
やっと授業が終わり、生徒たちは茫然自失の思いで廊下へ出る。卒業までこれが何回続くのだろう。まさに咎なくして死に体。音楽なんて嫌いだ。音楽そのものに罪は無いが、人は厭な思いをさせられた事象そのものを遺棄する。
これはやっかいな事に、あいなりもうした。お主これから後、如何なさるおつもりか。
先ほど、名札が出て無い、とUに指摘された森本君が、私の側に来て言う。どうして私の友達は、ここ一番という段になると、東映時代劇の下級武士に変身するのだろう。
―― 八 伏魔殿女名主 (了)
―― Page Top へ
―― 次章へ